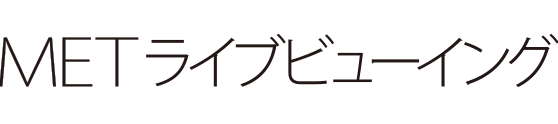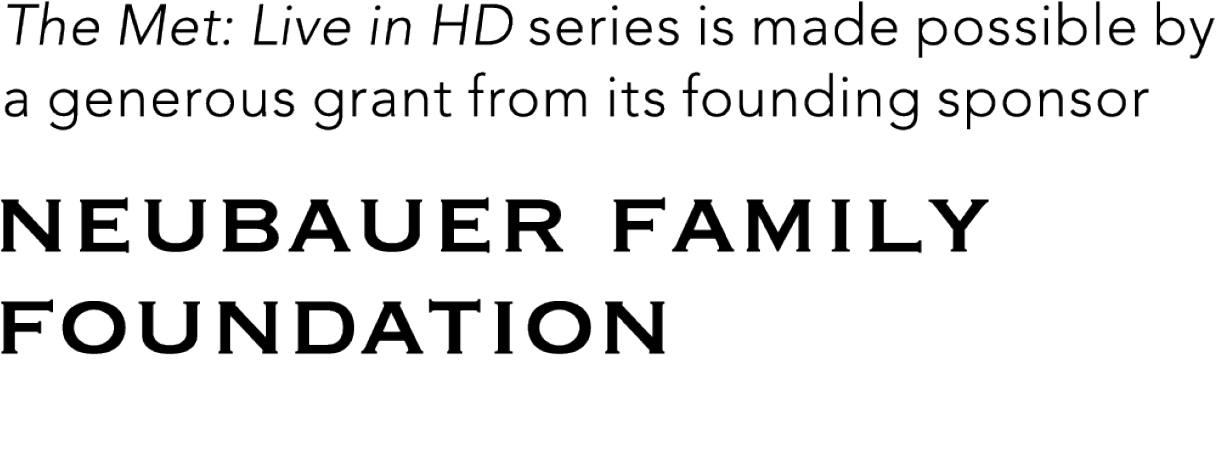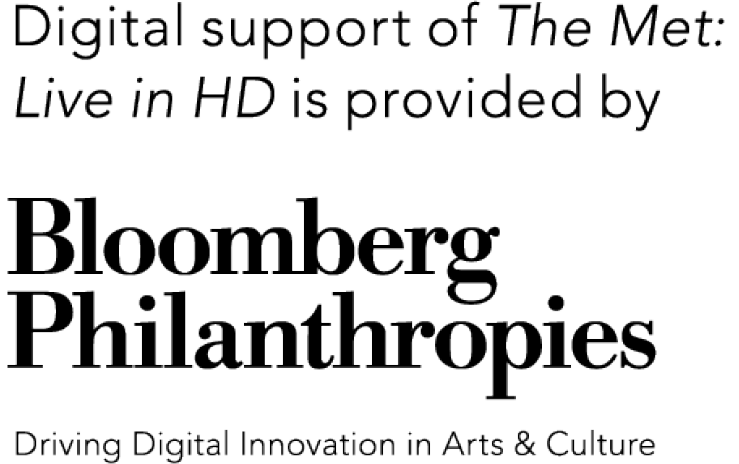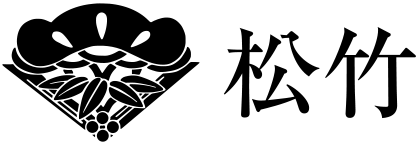《ルイザ・ミラー》現地レポート
音楽評論家 加藤浩子
これぞMET!これぞヴェルディ!
スター歌手と名指揮者が魅せた知られざる傑作の醍醐味!
 しびれる。
しびれる。
ヴェルディの音楽の魅力を一言で表現しろと言われたら、「しびれる」と答えたい。プッチーニが「とろける」愉悦なら、ヴェルディは「しびれる」快感だ。4月に現地METで観劇した《ルイザ・ミラー》は、まさに「しびれる」瞬間の連続だった。名作《リゴレット》や《椿姫》の数年前に作曲された《ルイザ・ミラー》は、ドイツの文学者シラーの戯曲にもとづいた「身分違いの恋」の悲劇を描くオペラである。それまで歴史絵巻的な作品が多かったヴェルディは、《ルイザ・ミラー》をきっかけに、より人物の内面に迫る心を打つ作品を書くようになった。実際《ルイザ・ミラー》には、後の名作の断片があちこちに聴かれる。
 第2幕で悪人のヴルムに偽の手紙を書かされるルイザに寄り添うクラリネットのメロディは、《椿姫》のヒロインが泣く泣く別れの手紙を書く場面と同じだし、大詰めのルイザとロドルフォの緊迫感溢れる二重唱は《オテッロ》の終幕の前触れだ。ルイザが父に抱かれて息をひきとる幕切れは、同じ状況の《リゴレット》の幕切れを予感させる。「いろんな要素が詰まった実験的な作品」(ロドルフォを歌ったP・ベチャワの言葉)とされるのももっともなのだ。
第2幕で悪人のヴルムに偽の手紙を書かされるルイザに寄り添うクラリネットのメロディは、《椿姫》のヒロインが泣く泣く別れの手紙を書く場面と同じだし、大詰めのルイザとロドルフォの緊迫感溢れる二重唱は《オテッロ》の終幕の前触れだ。ルイザが父に抱かれて息をひきとる幕切れは、同じ状況の《リゴレット》の幕切れを予感させる。「いろんな要素が詰まった実験的な作品」(ロドルフォを歌ったP・ベチャワの言葉)とされるのももっともなのだ。
 だがそんなことを知らなくとも、《ルイザ・ミラー》は十二分に楽しめる。情熱的で絶望的な恋に燃える若者たち、暗い過去を抱える伯爵とその部下、娘への愛と名誉の狭間で揺れる老いた父、初恋の男性を忘れられない誇り高い未亡人… 登場人物はそれぞれに個性的で、とても人間的だ。悪人と位置づけられる伯爵もヴルムも、それぞれ息子への愛、ルイザへの愛という弱みを持っている。人間味…それこそ、ヴェルディ・オペラを永遠たらしめている魅力のひとつだろう。そしてその魅力は、表現できる歌手や指揮者がいて初めて開花する。最高だった。
だがそんなことを知らなくとも、《ルイザ・ミラー》は十二分に楽しめる。情熱的で絶望的な恋に燃える若者たち、暗い過去を抱える伯爵とその部下、娘への愛と名誉の狭間で揺れる老いた父、初恋の男性を忘れられない誇り高い未亡人… 登場人物はそれぞれに個性的で、とても人間的だ。悪人と位置づけられる伯爵もヴルムも、それぞれ息子への愛、ルイザへの愛という弱みを持っている。人間味…それこそ、ヴェルディ・オペラを永遠たらしめている魅力のひとつだろう。そしてその魅力は、表現できる歌手や指揮者がいて初めて開花する。最高だった。
 ルイザ役S・ヨンチェヴァは高い技術と豊かな表現力を最大限に開花させ、ロドルフォ役ベチャワは安定度の高さに円熟を感じさせつつ、ヴェルディ作品に欠かせない情熱を惜しみなく溢れさせた。名アリア「穏やかな夜」では、当夜最大の喝采が炸裂した。
ルイザ役S・ヨンチェヴァは高い技術と豊かな表現力を最大限に開花させ、ロドルフォ役ベチャワは安定度の高さに円熟を感じさせつつ、ヴェルディ作品に欠かせない情熱を惜しみなく溢れさせた。名アリア「穏やかな夜」では、当夜最大の喝采が炸裂した。
 かつてMETの舞台で伝説的なロドルフォを歌ったP・ドミンゴは、40年を経て娘への情愛に満ちた老父になりきって客席を沸かせ、伯爵を歌ったA・ヴィノグラドフは罪の意識と息子への歪んだ愛への葛藤を声と演技で吐露し、ヴルムを歌ったD・ベロセルスキーは輝かしい響きのなかに人間的な弱さをにじませた。
かつてMETの舞台で伝説的なロドルフォを歌ったP・ドミンゴは、40年を経て娘への情愛に満ちた老父になりきって客席を沸かせ、伯爵を歌ったA・ヴィノグラドフは罪の意識と息子への歪んだ愛への葛藤を声と演技で吐露し、ヴルムを歌ったD・ベロセルスキーは輝かしい響きのなかに人間的な弱さをにじませた。

フェデリーカ役O・ペトロヴァの将来性にも期待したい。当初予定されていたレヴァインの代役として登場したB・ド・ビリーの指揮も、すべてを掌握した上で、時にひっそりと歌を生かし、時に歌と同化してドラマを推進した理想的なものだった。名人芸とは、こういうことを言うのだろう。
オペラに、その奇跡にしびれた一夜。映画館でもその空気は、十二分に体験できるはずだ。