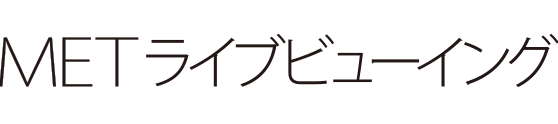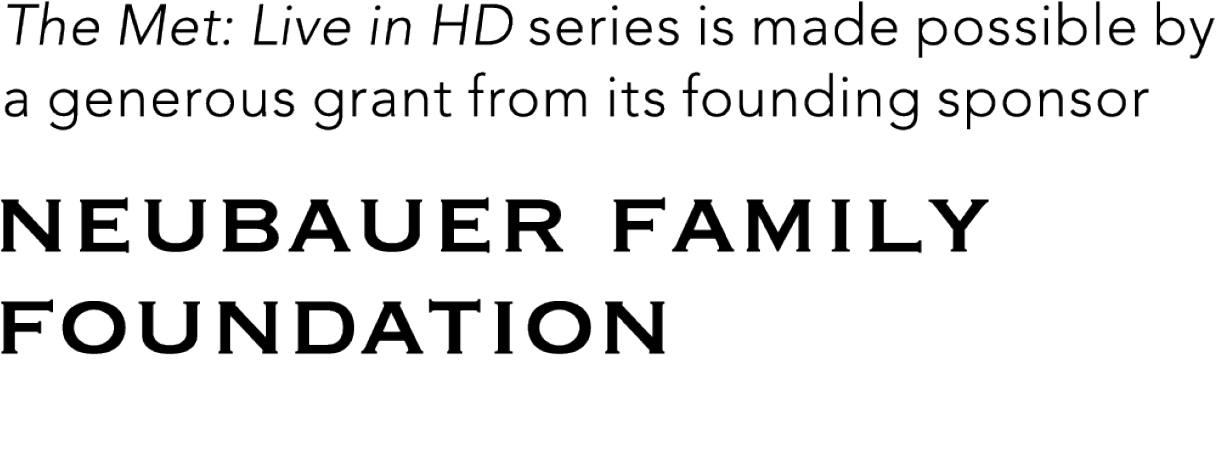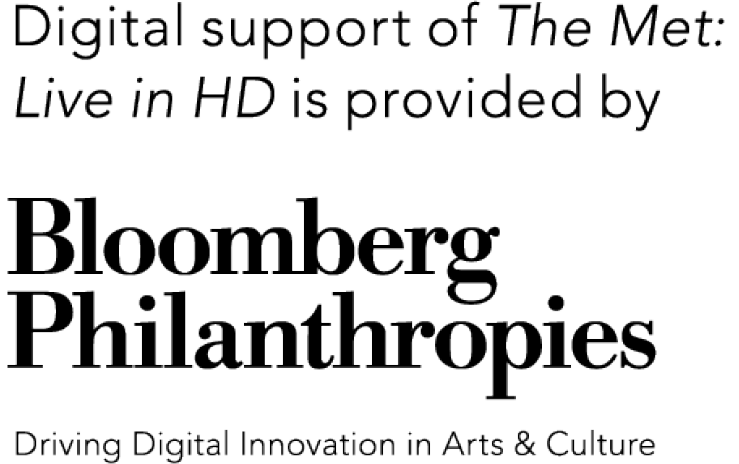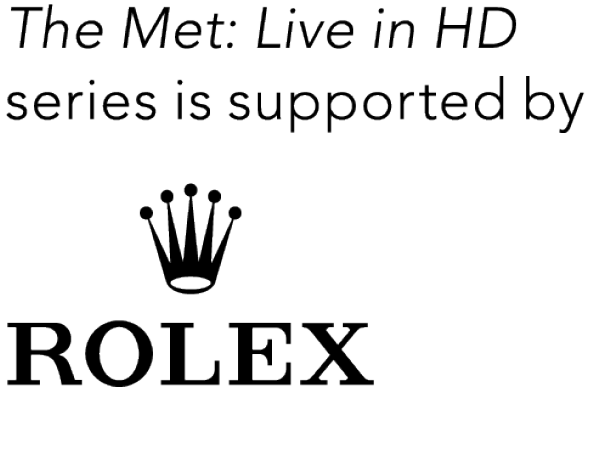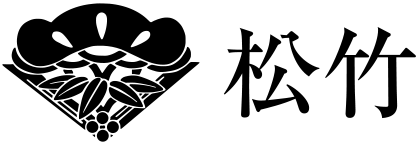《アイーダ》みどころレポート
2025年2月21日 金曜日
メトロポリタンオペラの新しい『アイーダ』を観て
演出家 粟國淳
僕はこれまで、日本はもとより、イタリアなど諸外国で公演されてきた様々なアイーダの公演を観てきました。今回のメトロポリタン歌劇場の公演映像を観ていると、その時々のアイーダ公演での演出のあり様や、出演歌手に感じた声色への驚きや、役に対する表情など、その記憶が自身の体から掘り起こされ、様々な演出での『アイーダ』が蘇ってきました。
若い頃に、いち観客として観た数々のアイーダ、そして舞台に関わり、演出家という仕事を生業とし、僕自身がアイーダの公演を演出する事になり、 仕事をする者の観点からのオペラアイーダへの記憶など、沢山の偉大なる先人演出家の作品に出会ってきました。
そして今回ここにご紹介する老舗中の老舗、メトロポリタン・オペラの新しい『アイーダ』を、僕自身もワクワクしながら拝見しました。
そして今回、メトの新制作のオペラ「アイーダ」を観ながら、私はまるでこの演出に登場する考古学者のような気持ちになったのです。
私が初めて『アイーダ』を観たのは、1973年、ローマのカラカラ浴場での公演で、僕はまだ7歳だったと思います。
このオペラに衝撃を受けたあの感覚、壮大な『凱旋行進曲』のテーマに合わせて行進する大勢のエキストラ、そして「グローリア・ア・エジット(エジプトに栄光あれ)」と歌う合唱の音の波!波!波!!。演出はブルーノ・ノフリ(NHKイタリア歌劇団でもいくつかの演出を手掛けた人物)、アムネリス役はフィオレンツァ・コッソットでした。その後も何度も『アイーダ』を観る機会があリましたが、その後私はついにカラカラの舞台にエジプト兵のエキストラとして立つことになったのです。特に印象に残っているのは、第2幕でアモナズロが王に向かって「その父だ!!」と叫ぶ場面は忘れることが出来ません。その一声の瞬間、客席からは大歓声が湧き起こり、「ブラーヴォ!」、「おかえり!」という声がカラカラの遺跡に座る観客から次々と飛んだのです。そう、その舞台に立っていたのは、事故から復帰したピエトロ・カプッチッリでした。
そして同じ年の12月、今度はローマ歌劇場での『アイーダ』に僕は再びエキストラとして出演しました。しかし、今回は兵士の役ではありませんでした。その理由は簡単、私の身長が役柄的に足りなかったのです。演出家の要求は身長180cm以上。しかし、私は170cmだったため、凱旋の場面で群衆の一人として、兵士たちを迎える側の役割となリました。そして、舞台の演出上、本物の馬がすぐ近くを通り、私はその迫力に圧倒されました。この公演の演出を手掛けたのはフランコ・ゼッフィレッリ。スカラ座のプロダクションで、アイーダ役はニーナ・ラウティオ、アムネリスはゲーナ・ディミトローヴァ、ラダメスはジュゼッペ・ジャコミーニ、指揮はダニエル・オーレンでした。それから5年後の1998年、私は再びゼッフィレッリの『アイーダ』に関わることになリました。それは、東京・新国立劇場のこけら落とし公演のための新制作「アイーダ」で、ゼッフィレッリの演出助手として、彼の助手としての役割でした。
こうして『アイーダ』を振り返ると、私自身の人生の様々な瞬間が、この作品とともにあったことに気づ来ます。思索、不安、喜び、悲しみ、感動、決断――まるで『アイーダ』の物語そのもののように。
『アイーダ』はジュゼッペ・ヴェルディの作曲によるオペラで、その物語は、フランスの著名なエジプト学者オーギュスト・マリエット(カイロのエジプト考古学博物館の創設者)によって考案されたものです。マリエットの構想を元に、フランスのリブレット作家カミーユ・デュ・ロックルがドラマの構成を練り、最終的にヴェルディにオペラ化を提案します。ヴェルディはこの作品を作曲することを決め、リブレットの執筆にはアントニオ・ギスランツォーニを指名しました。『アイーダ』は、スエズ運河開通を祝うためにエジプト総督(ケディーヴ)によって委嘱された作品です。しかし、このオペラは単なる祝典用の作品ではなく、プロパガンダ的な意図を持ちたくないヴェルディは、作曲の自由を保証された上で、この仕事を引き受け、芸術的妥協を一切許しませんでした。ヴェルディは緻密で慎重な作曲家で、彼は作品のリアリティを追求するため、メンフィスの神官たちの衣装、メンフィスからテーベまでの正確な距離、移動にかかる時間、パピルスに描かれた不思議な楽器の形状や音色など、細部に至るまで徹底的に調査をしました。その結果生まれたのが『アイーダ』のトランペットとも呼ばれる、長く細い一本ピストンのトランペットです。この楽器は『凱旋行進曲』の場面で数多く登場し、日本でも「アイーダ・トランペット」として知られています。
『アイーダ』は、大規模な合唱や『凱旋行進曲』の壮大さで知られていますが、実は非常に内面的なドラマでもあリます。愛、忠誠、義務の間で揺れ動く登場人物たちの心理が、オペラ全体に深い陰影を与えていて、アムネリスはしばしば単なる敵役と見られがちですが、実はこの作品の中でも最も人間的で、最も悲劇的なキャラクターの一人であります。彼女の激情と絶望は、他の登場人物とは異なるドラマを生み出し、ラムフィスや王もまた、単なる権力者ではなく、敗者への慈悲を示す存在として描かれています。アモナズロもまた、王としての責務を背負う人物であり、祖国を救うために個人的な感情を抑えざるを得ない宿命を持つ役柄です。ヴェルディは、こうした登場人物の感情を見事に音楽に織り込み、壮大なスペクタクルと繊細な叙情性を巧みに融合させています。その象徴とも言えるのが、アイーダとラダメスのデュエットであり、最後にアムネリスが「平和を、平和を」と静かに祈る終幕の場面です。彼女の言葉は、ラダメスの魂だけでなく、普遍的な「平和」への祈りとして響来ます。
メトの今回のマイケル・メイヤーの新演出は、『アイーダ』の壮大さと、その歴史を意識したものに見えます。原作の世界観を尊重しつつも、マリエットの視点を交えながら、物語の誕生そのものをも描こうとしているのかもしれません。
21世紀の技術を駆使しながら、過去と現在の『アイーダ』のバランスを取ろうとするメイヤーのアプローチ。最終的な評価は観客一人ひとりに委ねられますが、このメトロポリタン・オペラの新演出が、現代の観客に新たな視点を提供する試みであることは間違いなく。
歴史と伝統を豪華な衣装で纏いながらも、その歴史を誇りながらも、未来へと視点も合わせ、その歩みを続ける劇場。
それこそが、メトロポリタン・オペラなのだと思います。