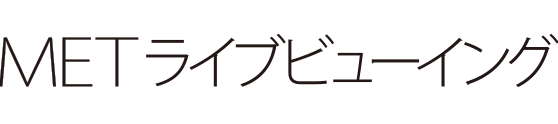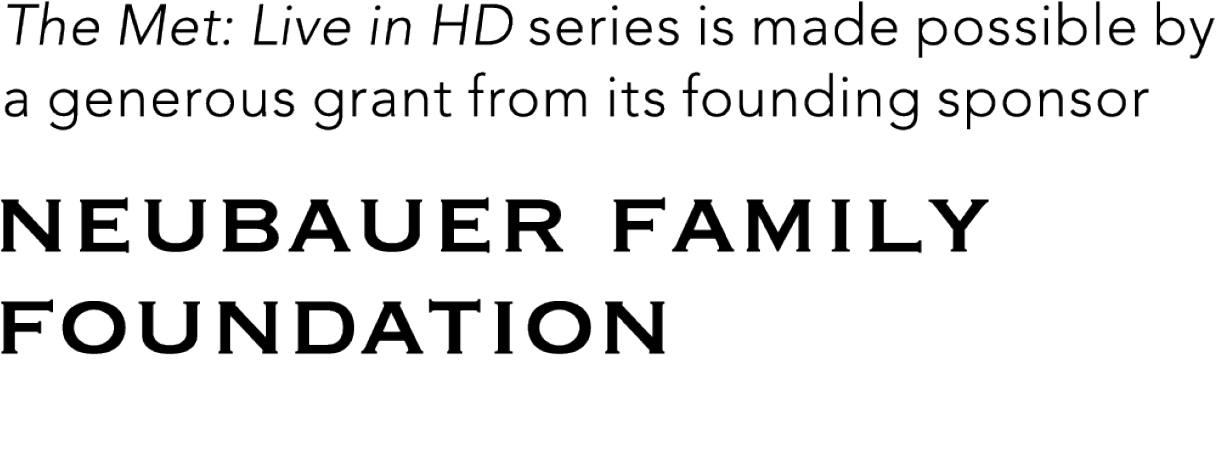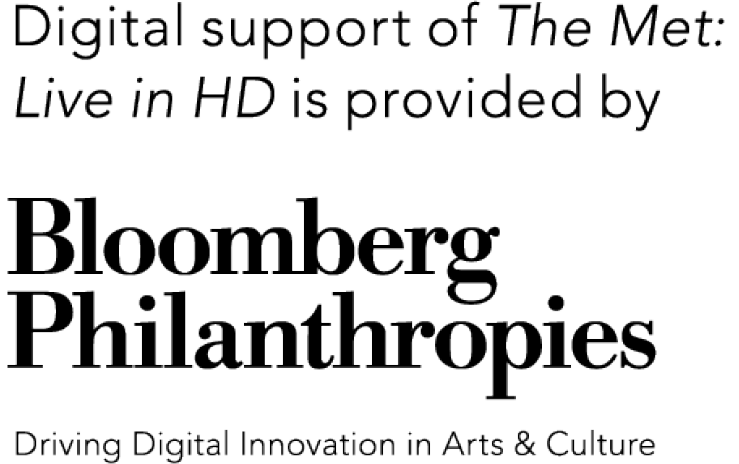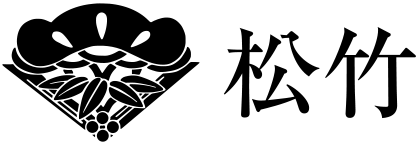《トスカ》みどころレポート
歌唱も管弦楽も演出もダイナミックにして繊細
興奮を抑えられない空前のリアリティ
オペラ評論家 香原斗志
鑑賞しながら1800年のローマにすっかり引きずり込まれ、興奮を抑えられなかった。《トスカ》はとりわけ人気のオペラだから上演機会も多く、筆者もこれまで数々の公演に感銘を受けたが、このMETの映像ほど、《トスカ》のポテンシャルが引き出された公演があったかどうか。思い出すのが難しい。

第1幕は聖アンドレア・デッラ・ヴァッレ教会が舞台だが、そこにパトリック・カルフィッツィが演じる堂守が入ってくると、もう興奮ははじまった。コミカルな動きと表情に声がしっかりと一致し、そのリアリティに目を見張ってしまった。
《トスカ》は3つの幕がみな実在の(しかも現存する)場所で展開する。演出のデイヴィッド・マクヴィカーはそれら3つの場所を、現地ロケではないかと思わせるほどのスケールおよび精度で再現し、人物の動きも表情も映画並みにつくり込んでいる。しかも、じつは人々の動きは、現代の観衆にとって自然なようにモダナイズされているが、それでいて1800年の出来事のように思わせてしまう。これも演出家の手腕である。
さらに特筆すべきは、演出を讃えるのに使った言葉が、そのまま音楽にあてはまることであった。スケールが大きく、かつ精密で、表情が豊か。結果としてリアリティに富んでいた。

カヴァラドッシ役のフレディ・デ・トマーゾは、筆者が注目しているイタリア系英国人のテノールで、最初のアリア「妙なる調和」から、本場では失われたようなイタリアの響きが力強く繰り出される。浴びるだけで心地よい官能的な声は、圧倒的な響きを誇りながら弱音までコントロールされ、細やかな表情をもつくり出す。

表題役を歌うのはリーゼ・ダーヴィドセン。トスカは激しい喜怒哀楽を、分厚いオーケストラを突き抜ける声で変幻自在に表現しなければならない難役で、並みのソプラノが歌うと、ところどころ絶叫になったり、音域によって声の質が変わってしまったりする。しかし、ワーグナーやR.シュトラウスを得意とするダーヴィドセンは、澄んだリリックな美声を、どんな音域でも余裕をもって均質に響かせ、声質を変えずに深い感情を載せる。なんという至芸だろう。そのうえ、悪漢のスカルピアがなんとしてもものにしたいと、不埒な欲望をいだくのも当然という美貌である。そのすべてにリアリティがある。
舞台上とは信じられないリアルなファルネーゼ宮殿内でのスカルピアとの対決では、手に汗握るという表現が比喩を超え、手のひらに汗がにじんでしまう。そのスカルピアを歌うクイン・ケルシーは厚い声で、無理な声色を使うことなく、この男の悪辣さや嫌らしさを余すところなく描く。
ヤニック・ネゼ=セガンは、これら歌手たちが織り成すドラマを、彼らが旋律に載せた真実の感情に寄り添いながら、オーケストラを鮮やかに指揮してドラマにリアリティを添えていた。そしてトスカが身を投げるまで、リアルな緊迫感の前に、手から汗が引くことはなかった。