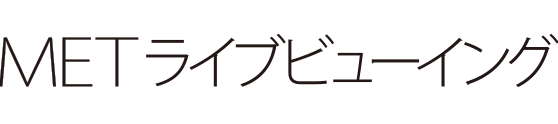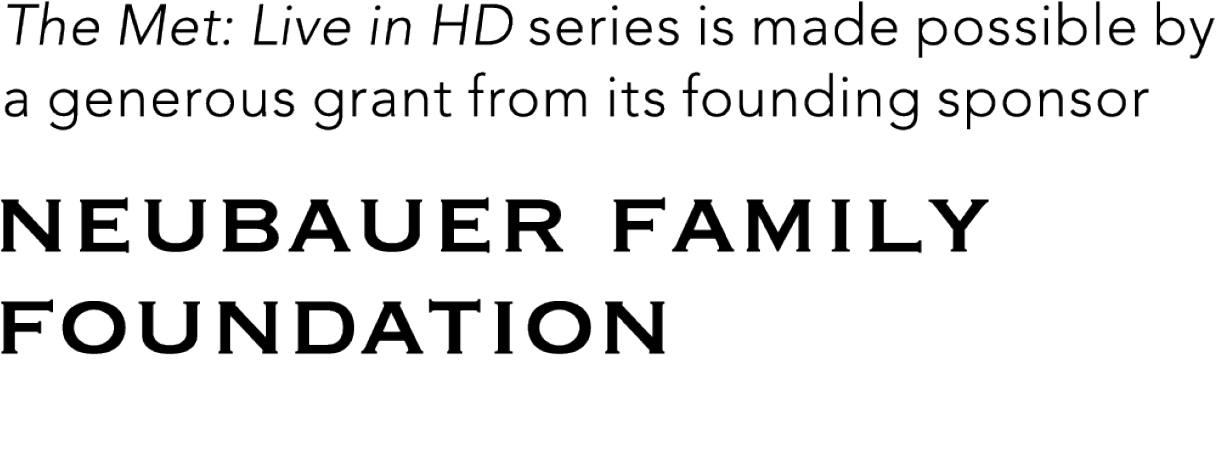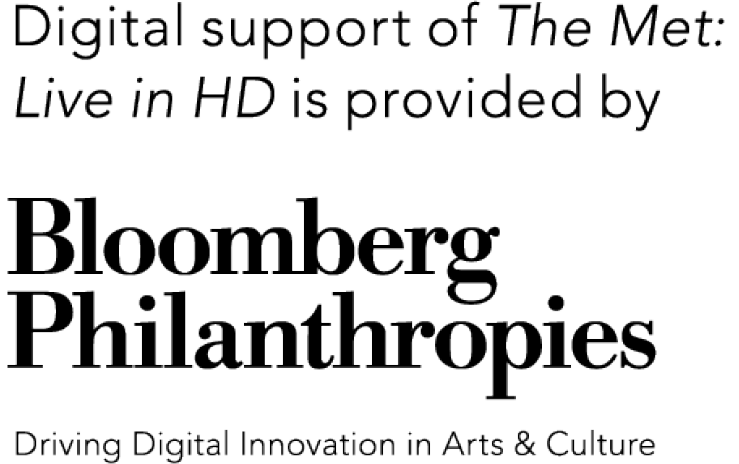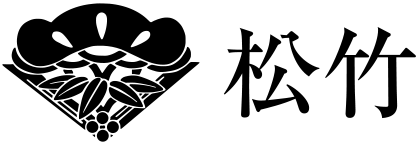《マルコムX》みどころレポート
音楽評論家 柳樂光隆
今、METに注目が集まっている。もはやオペラやクラシックの枠を超えて、というよりもこれまでオペラやクラシックに親しみがなかったひとたちを魅力している。その理由はMETが行っている新たな取り組みにある。アートにも多様性や平等、公平や公正が求められる中、様々な側面から社会問題にも取り組んできたMETがそのひとつとして、Black Lives Matter以降、アフリカン・アメリカンの作曲家による作品を積極的に扱うようになった。
2021年、MET史上初の黒人作曲家によるオペラとして、テレンス・ブランチャード による《Fire Shut Up in My Bones》が上演された。続く、2022年にはテレンス・ブランチャードが初めて手掛けたオペラ《チャンピオン》を上演。ジャズミュージシャンで、スパイク・リー作品の映画音楽でも知られるテレンス・ブランチャードによる音楽のすばらしさと、人種問題や性差別・性暴力など、今、語られるべきテーマを含んでいたことなどが高く評価され、大きな反響を巻き起こした。

そして、2023年、テレンス・ブランチャードの2作に続き上演されたのが、ジャズ・ピアニストのアンソニー・デイヴィスによる《マルコムX》だった。黒人公民権運動の活動家で、過激な路線を提唱した指導者としても知られるマルコムXは1992年にスパイク・リーの手で映画化されたことで知られているが、1985 年には既にオペラになっていた。それを手掛けたのがアンソニー・デイヴィスだった。1970年代に頭角を現し、フリージャズ寄りのコミュニティで即興だけでなく、前衛的な作曲家としても活動していた彼の手によるオペラはマルコムXが傾倒していたジャズを軸にした挑戦的なものだった。古典的なスウィングやビバップだけでなく、マルコムが存命だったころに勢いのあったジョン・コルトレーンらが演奏していたフリージャズのスタイルが織り込まれている楽曲はどれも当時の時代性を表しながら、同時にマルコムXのエピソードをパワフルに彩る。今回METで上演された2023年版ではそれをドラマーのジェフ・テイン・ワッツやトランペット奏者のアミール・エルサファーなど、現代の敏腕たちが奏でている。ジャズの伝統を身に着けたうえで、フリージャズのエネルギーをも的確に生み出すジャズミュージシャンたちの即興演奏はこのオペラの見せ場のひとつ。マルコムを演じるウィル・リバーマンの熱演に拮抗するような演奏に何度もハッとさせられる。

また、トゥラニ・デイヴィスの台本も素晴らしい。当時の人種差別の過酷さやそれに抵抗するマルコムの姿を生々しく描いているだけでなく、マルコムが受けた様々な思想的な影響やマルコムの深い思索なども反映されていることで、ただの伝記の枠を超え、スピリチュアルさや壮大さを感じられるものになっている。その世界観を的確かつ、大胆に拡張したような演出を施したのがロバート・オハラだ。衣装やセットにはアフリカや宇宙のモチーフが多用されているが、それらは当時のマルコムを取り巻く様々な状況だけでなく、当時の黒人たちを魅了したアフリカ回帰やアフロフューチャリズムの思想とも繋がっているもの。ここではその思想をSF的でもある特異なデザインを配置することで表現しているのだが、それさえも現代的なテクノロジーを駆使することでオペラの一部として完全に溶け込ませている。ここでのロバート・オハラの仕事は見事というほかない。一見、オルタナティブで、実験的な作品だが、すべてががっちり噛み合うことで、実に自然に表現できていて、観客はただただ没入できる。何から何までよくできているのだ。
2023年の年末、僕はアメリカのシンガーソングライターのミシェル・ンデゲオチェロにインタビューをした。アフリカ系アメリカ人としての自分たちの手で「新しい神話」を紡ぐ必要があるというような話をしてくれた。僕は《マルコムX》に感じたのはまさにミシェル・ンデゲオチェロが言っていたような意味での「新たな神話」を見ている感覚だった。古さでも新しさでもなく、あらゆる面で「普遍性」みたいなものを感じさせてくれる。《マルコムX》は作品を鑑賞したというよりは、特別な「体験」のような感覚を与えくれるオペラだと僕は思った。