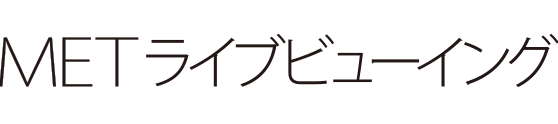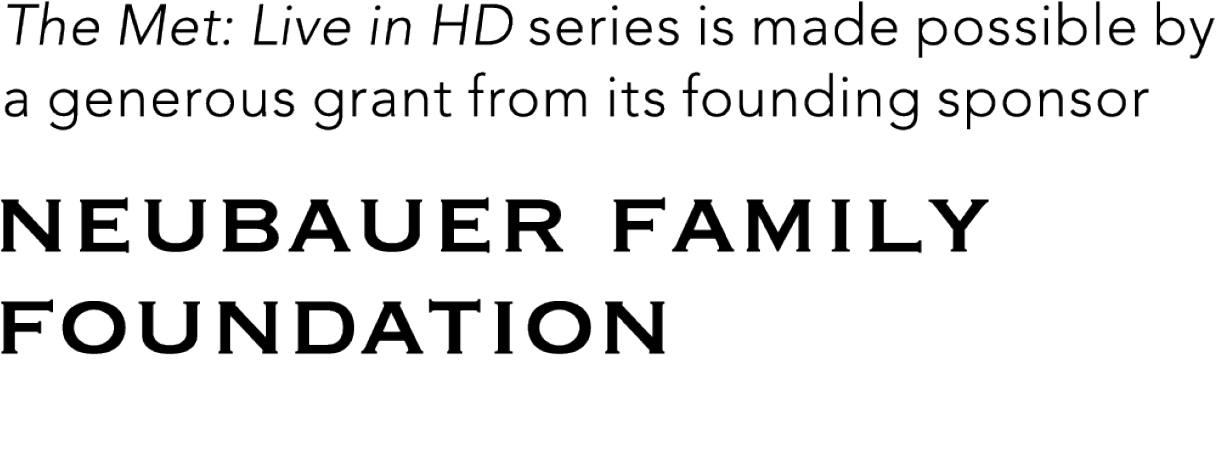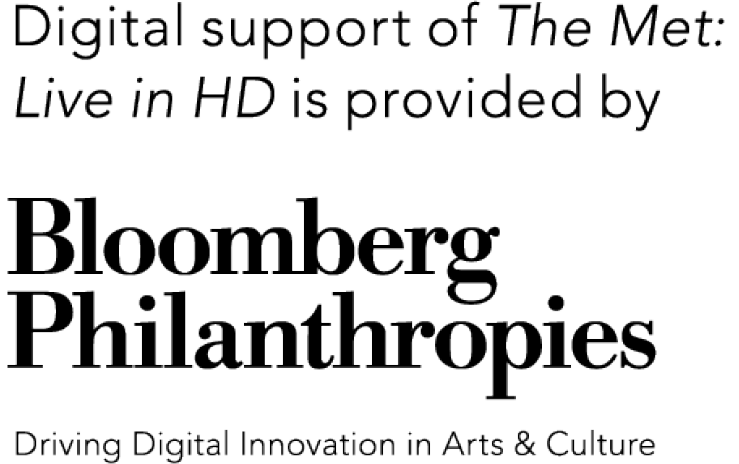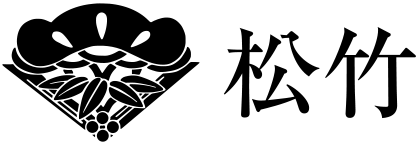《魔笛》みどころレポート
みずみずしい演奏、臨場感あふれる舞台、無限のファンタジー
かぎりなく上質で幸福を呼ぶMETの《魔笛》
オペラ評論家 香原斗志
序曲冒頭からすこぶる魅惑的だった。MET管弦楽団からこれほど古楽的な音が聴かれたことが、これまであっただろうか。指揮者は世界的な名コントラルト歌手として活躍したナタリー・シュトゥッツマン。古楽に精通した彼女の手で、《魔笛》が誕生したときに響いたであろう、シャープで生々しい音が生み出され、その音楽は、モーツァルトがたくらんだであろう刺激的な彩りにあふれていた。

この心躍らされる音楽が、サイモン・マクバーニーの演出と見事にからみ合い、相乗効果を生んでいた。《魔笛》は1791年、作品の台本も手がけたエマヌエル・シカネーダーが集合住宅のなかに開設した劇場で初演された。この大衆的な劇場では、おそらくオーケストラは舞台上にあって、客席と舞台との距離もとても近かっただろう。
マクバーニーは巨大なMETで、初演時の雰囲気を見事に再現した。歌手たちがいつもよりかなり浅いオーケストラ・ピットや客席の周囲を駆けまわるだけではない。ヴィジュアルアーティストがリアルタイムで文字や絵を描き、それがスクリーンに映し出される。また効果音も、専門のアーティストが目の前でいろんな道具を使って生み出し、その様子が客席から見える。
 METという世界最大級の劇場でこの心地よい臨場感は驚きだ。加えて、たとえばタミーノとパミーナの火と水の試練は、火や水の見事な映写と効果音で彩られ、とくに水の試練では2人が宙づりになって「泳いだ」。このように全、それでいてリアルな現代劇のようでもある。じつに奥が深い。
METという世界最大級の劇場でこの心地よい臨場感は驚きだ。加えて、たとえばタミーノとパミーナの火と水の試練は、火や水の見事な映写と効果音で彩られ、とくに水の試練では2人が宙づりになって「泳いだ」。このように全、それでいてリアルな現代劇のようでもある。じつに奥が深い。
そして、自身が歌手で、歌手の呼吸や生理を知り尽くしているシュトゥッツマンの指揮のもと、もともと力がある適材適所の歌手たちが躍動した。

タミーノ役のローレンス・ブラウンリーは、ベルカント・オペラで鍛えた比類ないテクニックを下地に、艶のある美声ときわめて安定したフォームで隙がない。パミーナ役のエリン・モーリーはまっすぐ伸びるなめらかな声が魅力的で、中低音域も安定し、感情表現も深い。パミーナを全曲とおして歌うのははじめてだというが理想的な歌唱だ。そこにパパゲーノ役のトーマス・オーリマンスが、コミカルな味わいを絶妙に加える。この歌手はどんなに滑稽味を表現しても歌い崩れることがない。
 また、スティーヴン・ミリングのザラストロは温もりのある低音で「太陽の世界」を思わせ、夜の女王のキャスリン・ルイックは、完璧に磨かれたテクニックと超高音で、音楽美を維持したままヒステリックな感情を描き「ダークサイド」を表現する。このように声によってこのオペラの世界観までが見事に表現される。
また、スティーヴン・ミリングのザラストロは温もりのある低音で「太陽の世界」を思わせ、夜の女王のキャスリン・ルイックは、完璧に磨かれたテクニックと超高音で、音楽美を維持したままヒステリックな感情を描き「ダークサイド」を表現する。このように声によってこのオペラの世界観までが見事に表現される。
マクバーニーは、今回の演出の原動力になったのはモーツァルトの「信念」だと語っていた。それは、フランス革命後のなにを信じればいいかわからない時代に、とてつもなく美しい音楽を書いて、劇場を出るまでに人々の意識を変える、という「信念」だったと。
その「信念」が今日の観客にとっても、かぎりなく強い力を持っている。そう思わせてくれる演奏と演出で彩られた、稀に見るすばらしい《魔笛》である。