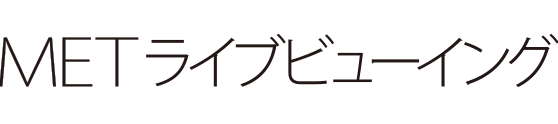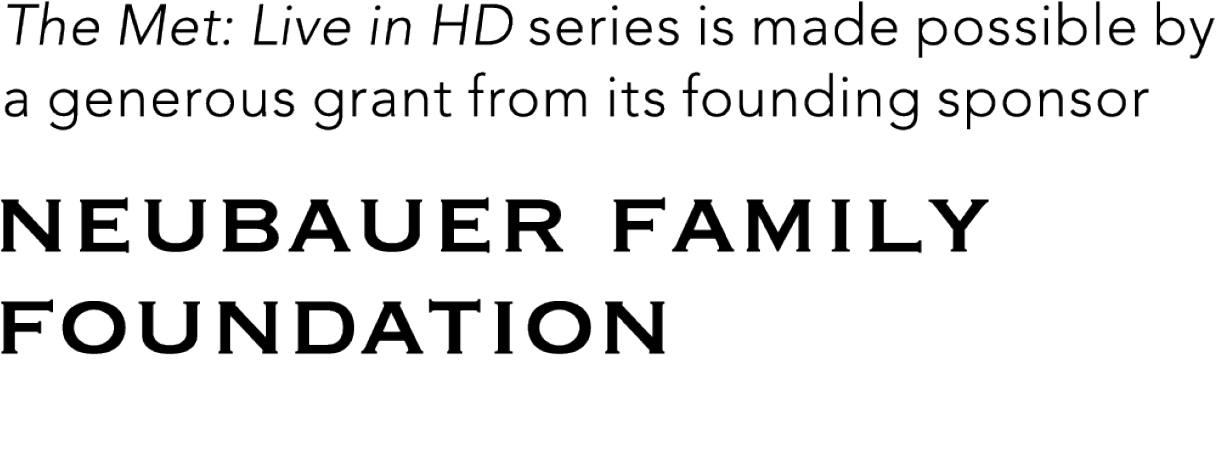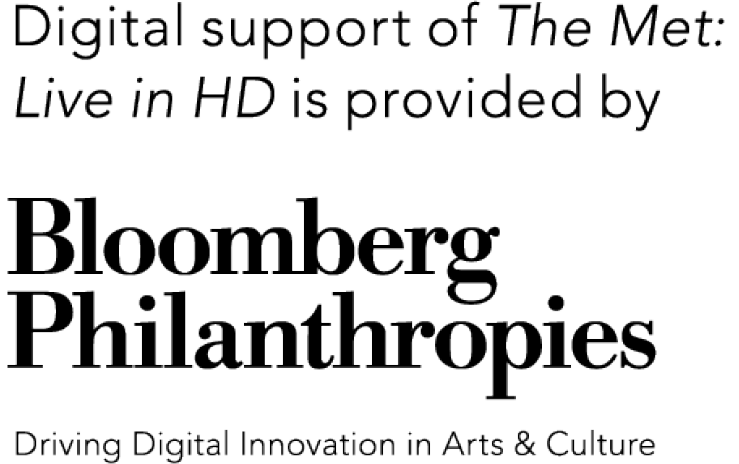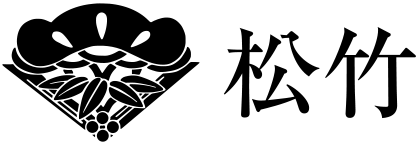MET初演!トーマス・アデス《皆殺しの天使》みどころレポート
岡部真一郎(明治学院大学教授/音楽学)
早熟の天才として、「現代のモーツァルト」「ブリテンの再来」などと呼ばれてきたトーマス・アデスも、四十代半ばを過ぎ、活動は一層の充実を見せている。先年、大成功を収めたルパージュ演出の《テンペスト》によりMETデビューを飾り、有数のオペラ作家としての名声を揺るぎないものとしたことも、周知の通りだ。

今回の新作、METがザルツブルク音楽祭、ロンドンのコヴェント・ガーデン王立歌劇場などと共同委嘱した《皆殺しの天使》は、シュールレアリスムの巨匠、ルイス・ブニュエルの同名の映画に基づく。
あらゆる合理的解釈を拒むかのような1962年の名画をアデスが初めて観たのは、少年時代のことというが、それには、美術史家でダリなどシュールレアリスムの権威である母の存在も、あながち無関係ではあるまい。

©Ken Howard/Metropolitan Opera
オペラ終演後、公爵夫人、医師、大佐、オペラ歌手、ピアニストら、12人の多彩なゲストたちが裕福な貴族の邸での晩餐に招かれる。しかし、様子がおかしい。使用人たちは、制止を振り切り、執事一人を残して皆、屋敷を離れてしまう。
食事を終え、夜は更け、客間のピアノの周りに集う客たちは、曙が訪れても、誰一人、帰ろうとしない。やがて、誰もが気づく。帰らないのではない、帰れないのだ。どうしても、客間から出ることができないのだ。

©Monika Rittershaus
シェイクスピア原作の前作《テンペスト》が「演劇についての演劇」、メタシアターであった流れを汲むかのように、《皆殺しの天使》は、いわば「オペラについてのオペラ」としての性格を持つ。観劇後の人々のストーリーを、われわれ観客は追う。
あたかも、公演をはねた後の自分たちの姿に重ねるかのように。舞台の夢物語と客席の現実との間の「結界」は、いとも容易(たやす)く崩れ去る。現実と非現実が交差する超現実の世界に誰もが引き込まれる。

©Ken Howard/Metropolitan Opera
アデスのスコアが、極めて緻密に書かれていることは見逃せない。例えば、作品冒頭。始めから幕が開いた舞台には、羊を引く男の姿、そして熊。このプロローグで聴こえる鐘には、オケのチューニングや指揮者の登場、そして本編の開始まで、細かくタイミングが指定されている。
加えて、原作でも重要な役割を果たすシーン反復。第1幕第3場では、客たちが玄関に到着する様子が2度に渡り描かれるが、2度目は、僅(わず)かにテンポを落とした上で、各パートのメロディーに絶妙に手が加えられ、変化が施されて、単なる繰り返しを越えた新たな光を放つ。

©Ken Howard/Metropolitan Opera
原作の様々なモティーフを巧みに活かしつつ、アデスはさらに、ディテールへの徹底したこだわりを見せる。それは、強さ、柔軟性と緻密さ、繊細さを兼ね備えた彼の音楽の魅力の源泉でもある。
全編を通じ、アンサンブル中心の書法は見事だが、一方、《テンペスト》でも圧巻の歌唱で耳目を集めたA・ルーナの超絶技巧、あるいは第3幕第3場、美しい2重唱の〈子守唄〉など、ヴェテランから若手まで、粒ぞろいのキャストによる聴かせどころは多い。
オペラ界の最先端を行く新たな名作を居ながらにして味わう――《皆殺しの天使》は、ライブビューイングの醍醐味を改めて実感する絶好の機会となろう。