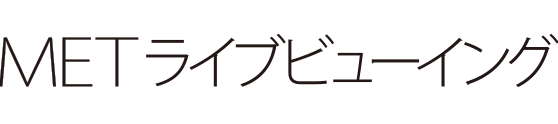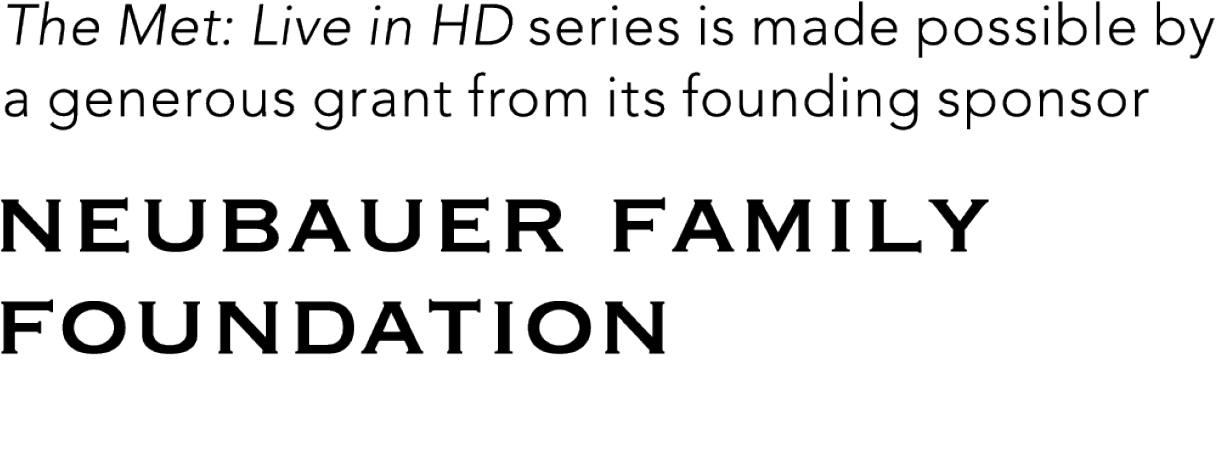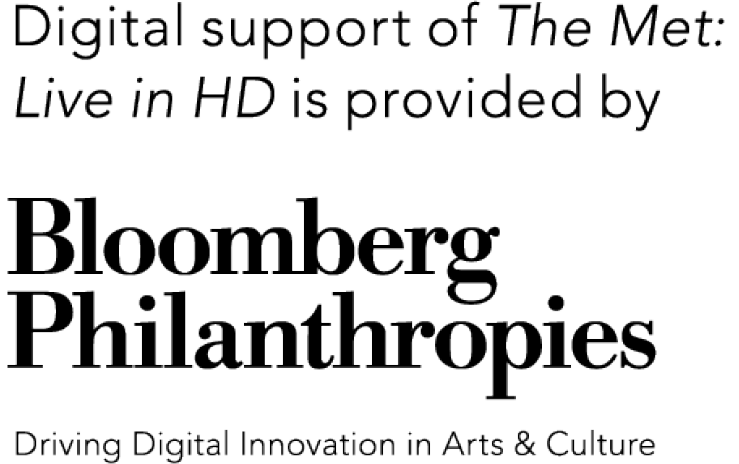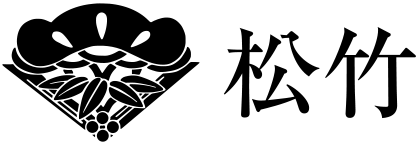《チャンピオン》みどころレポート
音楽ライター 小室敬幸
この舞台には完全なる悪人も、完全なる善人も登場しない。
だからこそ描ける、等身大の人間たちの欲望。
綺麗ごとで終わらせないリアルな物語は、
必ずやあなたの心の奥底に深く刻み込まれる――。
――温故知新の姿勢で刷新された、これぞ現代の大衆が感情移入できるオペラ
 METとして初めて上演した黒人作曲家によるオペラ《Fire Shut Up In My Bones》は、昨シーズンのMETのオープニングを飾り、大きな話題を呼んだ。作曲者はテレンス・ブランチャード。80年代、ウィントン・マルサリスやブランフォード・マルサリスらと共に伝統回帰を打ち出してデビューしてきたジャズミュージシャンたちのひとりだ。
METとして初めて上演した黒人作曲家によるオペラ《Fire Shut Up In My Bones》は、昨シーズンのMETのオープニングを飾り、大きな話題を呼んだ。作曲者はテレンス・ブランチャード。80年代、ウィントン・マルサリスやブランフォード・マルサリスらと共に伝統回帰を打ち出してデビューしてきたジャズミュージシャンたちのひとりだ。
そんな彼が、今から10年前、当時51歳の時に世界初演されたのがオペラ《チャンピオン》である。ブランチャードにとって初めてのオペラだが、これまで様々なアメリカの歌劇場で数多く再演が重ねられていることからも分かるように、初挑戦とは思えぬ成熟した内容をもった傑作だ。この度、METで新演出が制作された。
オペラとしてとにかく上手いのは、伝統的なレチタティーヴォ(語りに近い朗唱)とアリアを巧みに再構築した点にある。ジャズやブルース、もしくはミニマル風の短いフレーズを繰り返す音楽に、台詞を進めていくレチタティーヴォ的な役割を担わせているのに対し、登場人物の心情が深く吐露されるアリアでは、映画音楽的な表現が主となる。そうすることで実にオペラらしいメリハリがつけられているのだ(ブランチャードは名匠スパイク・リー監督の映画を長年手掛けてきた、映画音楽の巨匠でもある!)。
古臭くないのに、ちゃんと伝統とも繋がっている――こうした音楽の在り方は、ブランチャードのジャズに対するアティテュードとも共通しているのが興味深い。この温故知新の姿勢で描かれるのは、実話にもとづくボクシング元世界王者エミール・グリフィスの生涯だ。
――生涯忘れられぬ後悔への赦しは、誰が与えてくれるのか?
 虐待と育児放棄により、結果的に良い体格を手に入れてしまったエミールは、女性用の美しい帽子をつくる職人を目指していたのに、周囲の人々の思惑によって本人はやりたくもなかったボクシングの世界へ。同時に自らのセクシャリティーに気づき、「男らしさ」に悩むエミールは、自分を「ゲイ野郎」と罵る対戦相手を試合中に殴り殺してしまう……(エミールは知らないが、この対戦相手も自らの意向とは関係なく体調不良のまま試合出場させられていることが劇中で描かれている)。
虐待と育児放棄により、結果的に良い体格を手に入れてしまったエミールは、女性用の美しい帽子をつくる職人を目指していたのに、周囲の人々の思惑によって本人はやりたくもなかったボクシングの世界へ。同時に自らのセクシャリティーに気づき、「男らしさ」に悩むエミールは、自分を「ゲイ野郎」と罵る対戦相手を試合中に殴り殺してしまう……(エミールは知らないが、この対戦相手も自らの意向とは関係なく体調不良のまま試合出場させられていることが劇中で描かれている)。
「成功」を重ねているうちは見て見ぬふりもできたが、パンチドランカーの症状が出始めた頃から、誤魔化しはきかなくなっていく。重い認知症を患う晩年のエミールの姿に、胸を痛めない人はいないだろう。なんでこうなってしまったのか? 今風にいえば「親ガチャ」の問題なのか、それとも「自己責任」なのだろうか?
結論をいえばこのオペラでは、エミールを突き放して「悲劇」にもしないし、ご都合主義的な「赦し」も与えない。人生をドラマ風にし過ぎない非常にリアルな終わり方は、却って多くの人々の心に残るはず。観終わったあとも長い余韻のつづく、新たな傑作オペラであることは間違いない。
―― 一流揃いの出演者とスタッフによって作り込まれた隙のないプロダクション
 本作が手放しで褒められるクオリティに仕上げられているのは、作品の良さだけでなく、出演者とスタッフが一流揃いで、しっかりと能力が発揮できているからだ。まずは主役エミール・グリフィスを演じた3名が文句なしに見事。リトル・エミール(子役)のイーサン・ジョゼフも良かったが、ちゃんとプロボクサーに見える身体に仕上げたライアン・スピード・グリーンが最大の功労者だろう。
本作が手放しで褒められるクオリティに仕上げられているのは、作品の良さだけでなく、出演者とスタッフが一流揃いで、しっかりと能力が発揮できているからだ。まずは主役エミール・グリフィスを演じた3名が文句なしに見事。リトル・エミール(子役)のイーサン・ジョゼフも良かったが、ちゃんとプロボクサーに見える身体に仕上げたライアン・スピード・グリーンが最大の功労者だろう。
彼はMETで研鑽を積み、その後はウィーン国立歌劇場でも活躍した、国際的にみてもトップクラスの実力をもつバス・バリトン。指揮者ドゥダメルとの共演も多い、次世代のスターだ。声の良さは当然として、今回とりわけ素晴らしかったのはナイーブな青年時代から、自暴自棄になった壮年期までを見事に演じてみせたこと。演技力豊かな歌唱は、本作の根幹を担ったといって過言ではない。
そして認知症に苦しむ老年期のエミールを演じたエリック・オーウェンズにも最大級の拍手を贈りたい。この15年、METを支えてきた名歌手であるオーウェンズが、誇張なく巧みに認知症の人物を演じきってみせたからこそ、観客はエミールという役を自業自得だと見捨てられなくなってしまう。本作の割り切れなさ、善悪どちらにも振り切れない絶妙なバランスを最後に保っているのがオーウェンズの名演だったといえる。
演出は、本作の誕生にも深くかかわり、初演でも演出をしているジェイムズ・ロビンソン。エミール・グリフィスの少年時代から老年期まで75年の人生を、時系列を行き来しながら物語が進み、更には認知症の症状で過去と現在が混在する場面まであるという、演出家泣かせの複雑な構成にもかかわらず、観客にストレスを与えることなく分かりやすく伝えてみせる。映像を多用しながらも、説明臭くなっていないのも見事だ。
 そして、それら全てを見事にまとめあげているのがMETの音楽監督である指揮者ヤニック・ネゼ=セガンである。ブランチャードご指名の一流ミュージシャンが揃ったリズムセクション(ベースはマット・ブリューワー、ギターはアダム・ロジャース、ドラムはジェフ・テイン・ワッツだ!)を従えるというよりも、彼らのフィーリングを活かしてそこに自然とオーケストラを帯同させていく。なので、音楽がダサくなる瞬間がない。その場にかかわる全員がちゃんと能力を発揮できている――オペラの内容とも繋がる重要なことを体現できているからこそ、オペラ《チャンピオン》は現代の大衆が違和感もつことなく感情移入ができる物語だと断言できるのだ。
そして、それら全てを見事にまとめあげているのがMETの音楽監督である指揮者ヤニック・ネゼ=セガンである。ブランチャードご指名の一流ミュージシャンが揃ったリズムセクション(ベースはマット・ブリューワー、ギターはアダム・ロジャース、ドラムはジェフ・テイン・ワッツだ!)を従えるというよりも、彼らのフィーリングを活かしてそこに自然とオーケストラを帯同させていく。なので、音楽がダサくなる瞬間がない。その場にかかわる全員がちゃんと能力を発揮できている――オペラの内容とも繋がる重要なことを体現できているからこそ、オペラ《チャンピオン》は現代の大衆が違和感もつことなく感情移入ができる物語だと断言できるのだ。