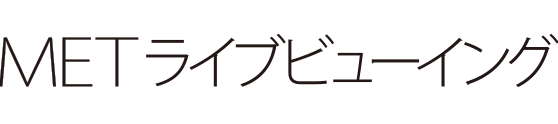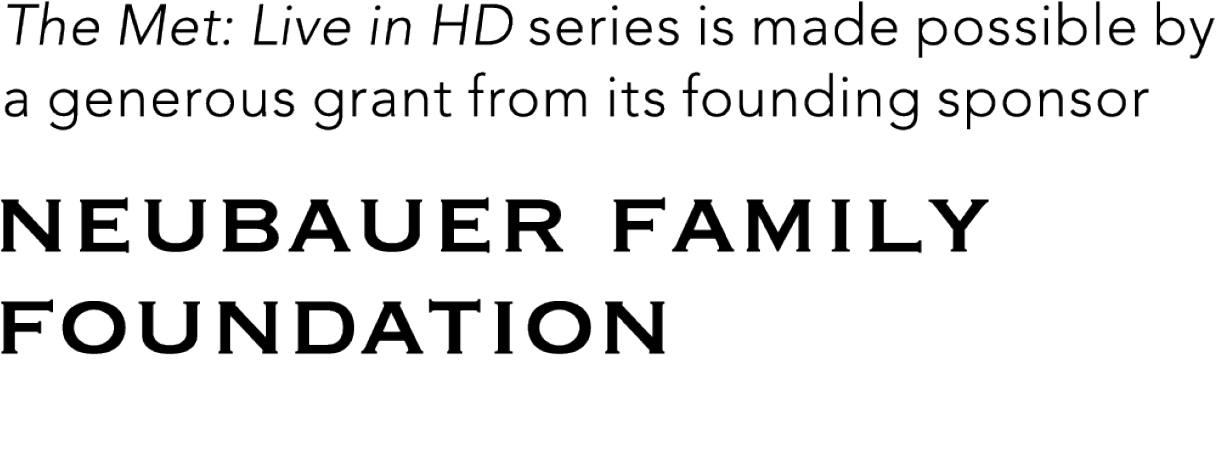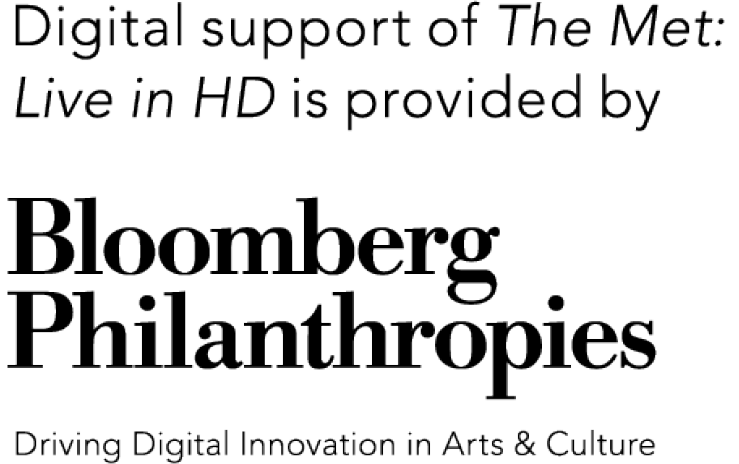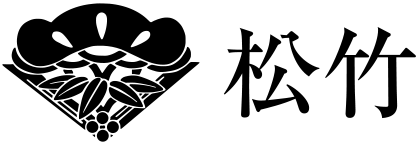《ファルスタッフ》みどころレポート
軽妙洒脱で、エレガントで、心地よくて、幸福になれる
すべての魅力が引き出されたMETの《ファルスタッフ》
オペラ評論家 香原斗志

心地よい笑いに誘われ、幕が下りたあとは、上等なカシミヤの毛布にでも包まれたかのような幸福感に包まれる。《ファルスタッフ》というオペラは、とびきりの舞台を鑑賞したときにかぎってだが、こんな気持ちにさせられる。METの《ファルスタッフ》はまさにそういう舞台だった。
作曲したヴェルディは、このオペラを書き上げたとき79歳。ほぼ悲劇ばかりを書いてきて、キャリアの最後に、主人公が懲らしめられながらも大団円で終わる喜劇を書いたのは、人間はどんなに立場が違っても共存できる、そうすればみんなが幸福になれる、と伝えたかったからではなかったか。
 指揮者のダニエレ・ルスティオーニは、作品に込められたそんなメッセージを、ヴェルディの巧妙な仕かけを魅力的に奏しながら鮮やかに引き出していた。
指揮者のダニエレ・ルスティオーニは、作品に込められたそんなメッセージを、ヴェルディの巧妙な仕かけを魅力的に奏しながら鮮やかに引き出していた。
なにしろ第1幕冒頭のシンコペーションから、聴き手の耳を一気に釘づけにするほど軽やかでシャープで、そのまま観客をドラマに引き込んでしまう。

このオペラでは洗練された詩句が、言葉に合わせて採寸されたオーダーメイドの衣装のような音楽と見事に一体になっているが、ルスティオーニが導く音楽は、ファルスタッフをはじめとする登場人物たちの軽妙で洒脱な言葉と動作そのものだ。しかも、そこにエレガンスが漂う。
たとえば第1幕第2場。4人の女声、5人の男声、若いカップル……と、舞台上の主役は次々と替わるが、音楽は起伏が強調されながらも途切れない。大きな川の流れに、色彩や模様が異なる花火を次々と鮮やかに映し出すかのようだ。観客は上質な音楽に身をまかせ、心地よさを味わいながらそれぞれの場面を堪能できる。

また、このオペラはアンサンブルを連ねて物語が進んでいく。ルスティオーニの言葉を借りれば、精巧な時計のようで歯車がひとつでも合わないとダメだが、終始一貫して見事なアンサンブルだった。
 タイトルロールのミヒャエル・フォレはワーグナーが得意なドイツのバリトン。イタリア語が重要なファルスタッフ役にはどうかと疑いもしたが、これが徹頭徹尾見事なファルスタッフ。語るように歌いながらすべてが上等な音楽になり、驚いたことにイタリア語がとても美しい。
タイトルロールのミヒャエル・フォレはワーグナーが得意なドイツのバリトン。イタリア語が重要なファルスタッフ役にはどうかと疑いもしたが、これが徹頭徹尾見事なファルスタッフ。語るように歌いながらすべてが上等な音楽になり、驚いたことにイタリア語がとても美しい。
アリーチェのアイリーン・ペレス(ソプラノ)はアメリカ、フォードのクリストファー・モルトマン(バリトン)はイギリス、クイックリー夫人のマリー=ニコル・ルミュー(コントラルト)はカナダ、ナンネッタのヘラ・ヘサン・パク(ソプラノ)は韓国と、イタリア人がいない国際キャストなのに、イタリア語のアンサンブルがここまで見事なのも、うれしい驚きである。一人挙げれば、パクの自然に息に乗せられコントロールの行き届いた美しい歌唱は特筆に値する。
舞台を1950年代に移したロバート・カーセンの、配慮が行き届き洗練された演出も、エレガントで軽妙洒脱な音楽とぴったりで、私自身、見終わっていまなお心地よさが持続している。