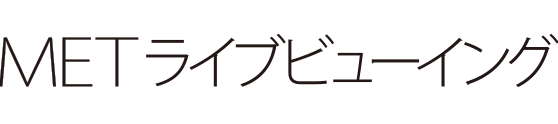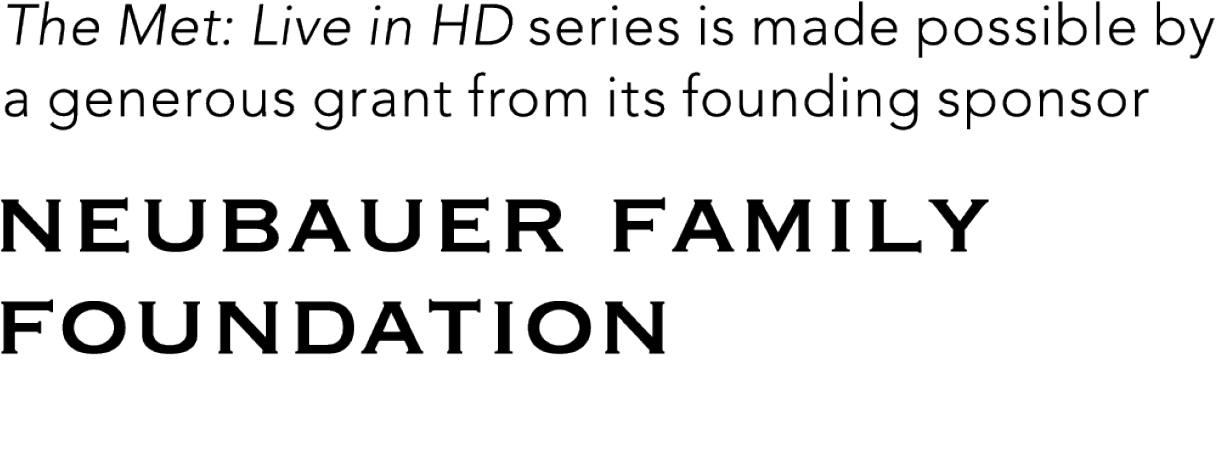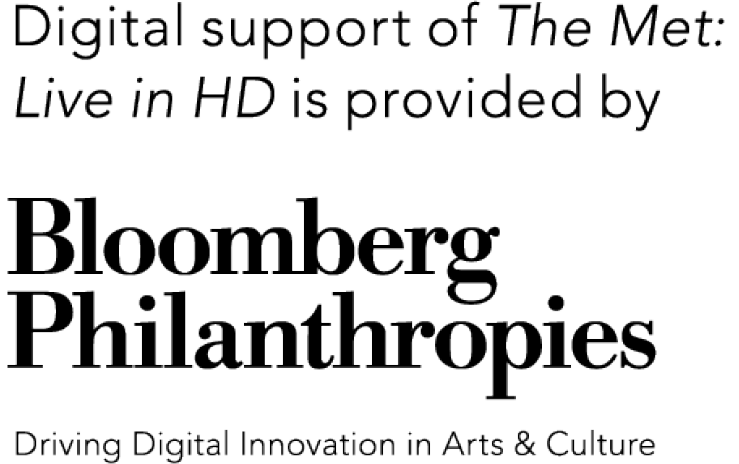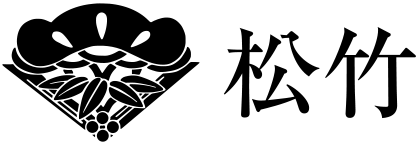《めぐりあう時間たち》みどころレポート
著述家、プロデューサー 湯山玲子
 「オペラを芸術形式として前進させていくためには新作を世に送り出していくことが重要だ」とは、MET総裁のピーター・ゲルブ氏の言葉だが、METはオペラの歴史的マスターピースとともに、意欲的に新作を世に出し続けていることでも名高い。
「オペラを芸術形式として前進させていくためには新作を世に送り出していくことが重要だ」とは、MET総裁のピーター・ゲルブ氏の言葉だが、METはオペラの歴史的マスターピースとともに、意欲的に新作を世に出し続けていることでも名高い。
古典オペラの舞台背景を現代アメリカのラストベルトにしたり、場合によっては、宇宙空間まで飛び出すような演出上の試みではなく、ゼロから一を生んでいくようなクリエイティビティ。METの凄いところは、オペラファン以外の文化系にも届くような(とはいえ、ポピュリズムからはほど遠い)、良質なエンターテイメントとしての新作を実現していくその実力にある。
 さて、METが昨年秋に世界初演した《めぐりあう時間たち》は、「そう来たか?!」という時代性と題材セレクトの妙が光る大変に魅力的な新作になった。文学史にその名を残す、女流作家、ヴァージニア・ウルフの小説『ダロウェイ夫人』を巡り、異なる時代に生き、それぞれに問題を抱えている3人の女性(その中に当の小説家自身も入る)それぞれの運命の一日を描いたマイケル・カニンガムの小説を基にし、最初のオペラ『静かな夜』がピューリッツァー賞を受賞したことで名高いケヴィン・プッツの作曲にてオペラ化。ちなみに、同作は2002年に映画化され、第75回アカデミー賞で9部門にノミネート。ニコール・キッドマンがアカデミー主演女優賞を受賞したことでも名高い。
さて、METが昨年秋に世界初演した《めぐりあう時間たち》は、「そう来たか?!」という時代性と題材セレクトの妙が光る大変に魅力的な新作になった。文学史にその名を残す、女流作家、ヴァージニア・ウルフの小説『ダロウェイ夫人』を巡り、異なる時代に生き、それぞれに問題を抱えている3人の女性(その中に当の小説家自身も入る)それぞれの運命の一日を描いたマイケル・カニンガムの小説を基にし、最初のオペラ『静かな夜』がピューリッツァー賞を受賞したことで名高いケヴィン・プッツの作曲にてオペラ化。ちなみに、同作は2002年に映画化され、第75回アカデミー賞で9部門にノミネート。ニコール・キッドマンがアカデミー主演女優賞を受賞したことでも名高い。
 オペラ新作というと、親和性の高い神話ロマンやスペクタクル(衣装も装置も派手かつ分かりやすい)をお手軽に持ってきそうなところを、この作品は、女性の生き方や人間心理の不可解さ、そして、死の存在という純文学領域のテーマに肉薄。選び抜かれた言葉が炸裂する戯曲や、現代音楽的なアプローチとロマンシズムが同居する音楽とともに、非常に演劇的な仕掛けを張り巡らせているところに、このプロダクションの妙味がある。ウルフの小説の書き出しでも登場する「花」は、舞台上に幾度となく登場し、性愛や時の移ろいやすさを象徴。オペラの源流でもあるギリシャ悲劇のコロスのごとくの合唱と群舞が、3人の女性たちの言葉にならない内面の声、心象風景をひたひたと伝えてくれるのだ。
オペラ新作というと、親和性の高い神話ロマンやスペクタクル(衣装も装置も派手かつ分かりやすい)をお手軽に持ってきそうなところを、この作品は、女性の生き方や人間心理の不可解さ、そして、死の存在という純文学領域のテーマに肉薄。選び抜かれた言葉が炸裂する戯曲や、現代音楽的なアプローチとロマンシズムが同居する音楽とともに、非常に演劇的な仕掛けを張り巡らせているところに、このプロダクションの妙味がある。ウルフの小説の書き出しでも登場する「花」は、舞台上に幾度となく登場し、性愛や時の移ろいやすさを象徴。オペラの源流でもあるギリシャ悲劇のコロスのごとくの合唱と群舞が、3人の女性たちの言葉にならない内面の声、心象風景をひたひたと伝えてくれるのだ。
 3人の女性役に、ルネ・フレミング、ケリー・オハラ、ジョイス・ディドナートという、当代きっての歌手たちがキャスティングされているのも見どころ。マイクを通したポップスの、ナチュラルな歌声に普段親しんでいる現代人の耳には、オペラ的な発声は確かに耳慣れないものだが、名歌手たちの手にかかると、それがまったく違和感なく感じられる。違和感どころか、「心の声」のような、真相を伝えてくるその表現力に驚かされるだろう。3者それぞれのモノローグが絡む三重唱は、オペラならではの魅力を余す事なく伝えるとともに、こういった時空を越える表現方法を、オペラが伝統的に持っていたという、その現代性にも注目したい。
3人の女性役に、ルネ・フレミング、ケリー・オハラ、ジョイス・ディドナートという、当代きっての歌手たちがキャスティングされているのも見どころ。マイクを通したポップスの、ナチュラルな歌声に普段親しんでいる現代人の耳には、オペラ的な発声は確かに耳慣れないものだが、名歌手たちの手にかかると、それがまったく違和感なく感じられる。違和感どころか、「心の声」のような、真相を伝えてくるその表現力に驚かされるだろう。3者それぞれのモノローグが絡む三重唱は、オペラならではの魅力を余す事なく伝えるとともに、こういった時空を越える表現方法を、オペラが伝統的に持っていたという、その現代性にも注目したい。
 そして、なんといってもこの作品が、フェミニズムやLGBTQの問題を大きく内包しているところに注目したい。SNSの登場による世界的な#me too運動に代表されるように、時代はフェミニズムの潮流の中にあり、この作品は女性が内包するミソジニー(女嫌い)、社会において、良妻賢母以外の居場所がないという疎外感、また、同性愛、母と息子の悩ましい関係性などをパッションの中に浮き彫りにしていく。
そして、なんといってもこの作品が、フェミニズムやLGBTQの問題を大きく内包しているところに注目したい。SNSの登場による世界的な#me too運動に代表されるように、時代はフェミニズムの潮流の中にあり、この作品は女性が内包するミソジニー(女嫌い)、社会において、良妻賢母以外の居場所がないという疎外感、また、同性愛、母と息子の悩ましい関係性などをパッションの中に浮き彫りにしていく。
主役である3人の歌姫たちの、舞台役者ばりの演技力にも注目。そう、オペラとはクラシック音楽の範疇で語られることが多い我が国だが、実は歌唱力とともに演技力が評価の基準ともなるのが本場のオペラなのです。