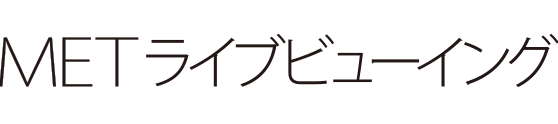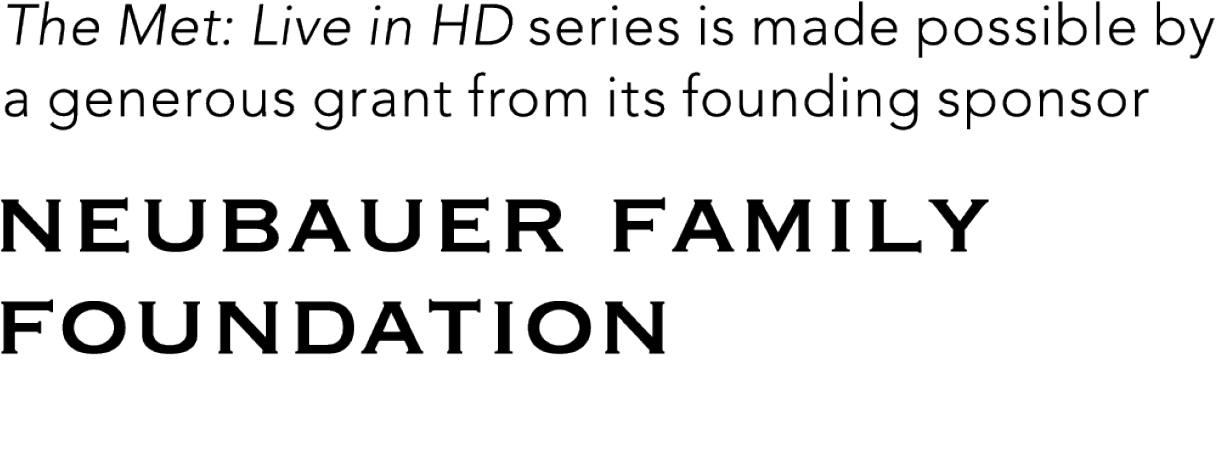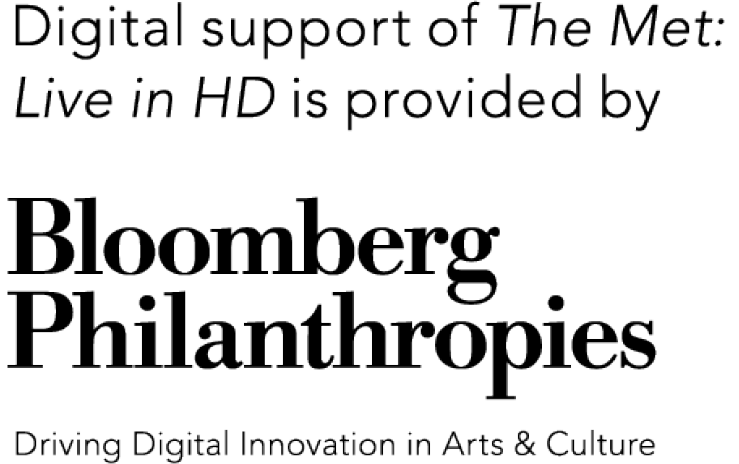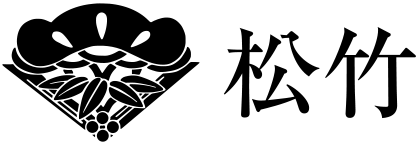《椿姫》みどころレポート
フリーアナウンサー、大学教授 八塩圭子
 《椿姫》ほど感情が揺さぶられて、涙するオペラはない。しかも、今、旬だと言われるネイディーン・シエラのヴィオレッタは、自然な発声、歌声に、豊かな表現力と演技が加わって、感情移入しやすいことこの上ない。クライマックスに歌われるヴィオレッタのアリア《さらば過ぎし日よ》では、涙を堪えられない。
《椿姫》ほど感情が揺さぶられて、涙するオペラはない。しかも、今、旬だと言われるネイディーン・シエラのヴィオレッタは、自然な発声、歌声に、豊かな表現力と演技が加わって、感情移入しやすいことこの上ない。クライマックスに歌われるヴィオレッタのアリア《さらば過ぎし日よ》では、涙を堪えられない。
このオペラはまさにヴィオレッタの「過ぎし日」が、回想されるがごとく描かれたストーリーなのだということが、マイケル・メイヤーの演出で強調されている。第1幕の前奏曲の際、死の床に臥せっているヴィオレッタを、アルフレードやジェルモンが暗い表情で囲んでいる。不穏な空気と悲しげなメロディの前奏曲でヴェルディが悲劇の最後を予感させたのだとしたら、ふさわしい演出だ。命が消えゆく際に、走馬灯のように思い出が巡るとよく言うが、第1幕、第2幕、第3幕と、愛しい人との出会いとときめき、別れと悲しさを走馬灯のように振り返っていく。それに合わせて舞台は春から、夏、秋、冬と移ろいゆく。出会いの春ではあんなに幸せそうだったのに、雪が舞う冬に別れを迎えるとは、心が締め付けられるような切なさを感じる。
 ヴィオレッタの死というクライマックスただ一点に向けて展開していく物語だなんて、悲劇の極地ではないか。それを意識して聴くと、社交界の華と若くて純な青年との胸躍る出会いの場面で歌われる〈乾杯の歌〉も、真実の愛か刹那的な快楽かで揺れる心を表現する〈ああ、そはかの人か~花から花へ〉も、さらに美しく尊く感じられる。
ヴィオレッタの死というクライマックスただ一点に向けて展開していく物語だなんて、悲劇の極地ではないか。それを意識して聴くと、社交界の華と若くて純な青年との胸躍る出会いの場面で歌われる〈乾杯の歌〉も、真実の愛か刹那的な快楽かで揺れる心を表現する〈ああ、そはかの人か~花から花へ〉も、さらに美しく尊く感じられる。
ライブビューイングだからこその歌手の細やかな表情まで追えるところも、感情移入しやすい理由の一つだ。常に安定して音楽を紡いでいるシエラの歌声の一方、彼女の表情は、落胆したり、自嘲したり、苦悶したりを見事に表現している。〈さらば過ぎし日よ〉を歌うシエラの目から一筋の涙が流れるシーンを見て、泣かずにいられようか。
 アルフレードとジェルモンも役柄とストーリー的には、「なんで信じてあげられない?」、「自分のことばっかり考えてないか?」と反発を覚えるのだが、それぞれを演じるスティーヴン・コステロ、ルカ・サルシの歌声と演技に免じて許してあげたくなる。そもそも、ヴィオレッタは2人を責める気などないのだから。
アルフレードとジェルモンも役柄とストーリー的には、「なんで信じてあげられない?」、「自分のことばっかり考えてないか?」と反発を覚えるのだが、それぞれを演じるスティーヴン・コステロ、ルカ・サルシの歌声と演技に免じて許してあげたくなる。そもそも、ヴィオレッタは2人を責める気などないのだから。
タイトルの「椿姫」=「ラ・トラヴィアータ」には、「道を踏み外した女」という意味がある。ヴィオレッタは高級娼婦ということなので、確かに道を踏み外したと言われればそうかもしれない。ただ、この舞台で描かれるヴィオレッタは、むしろピュアで真っ当な女性だ。道を踏み外すどころか、アルフレードに向いた一途の道をそれることなくひたすら歩いている。ヴィオレッタの衣装が、白、あるいは抑えめのゴールドという、華美でなくシンプルなドレスであったことで、その真っ直ぐさを象徴しているようにも感じた。
 椿は日本はじめアジアが原産の花で、それがヨーロッパに伝わって、新しもの好きのパリ社交界でブームになったのだとか。日本での椿の花言葉は「ひかえめの愛」。ヴィオレッタの本質はこちらの方がむしろ合っている気がする。
椿は日本はじめアジアが原産の花で、それがヨーロッパに伝わって、新しもの好きのパリ社交界でブームになったのだとか。日本での椿の花言葉は「ひかえめの愛」。ヴィオレッタの本質はこちらの方がむしろ合っている気がする。
是非、皆様も、ひかえめな愛を貫く主人公の気分を味わい、ときめき、幸せを感じ、絶望し、泣いて、感情を揺さぶられに映画館へ。今年1年分の心のデトックスになるはずだ。