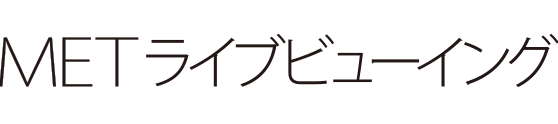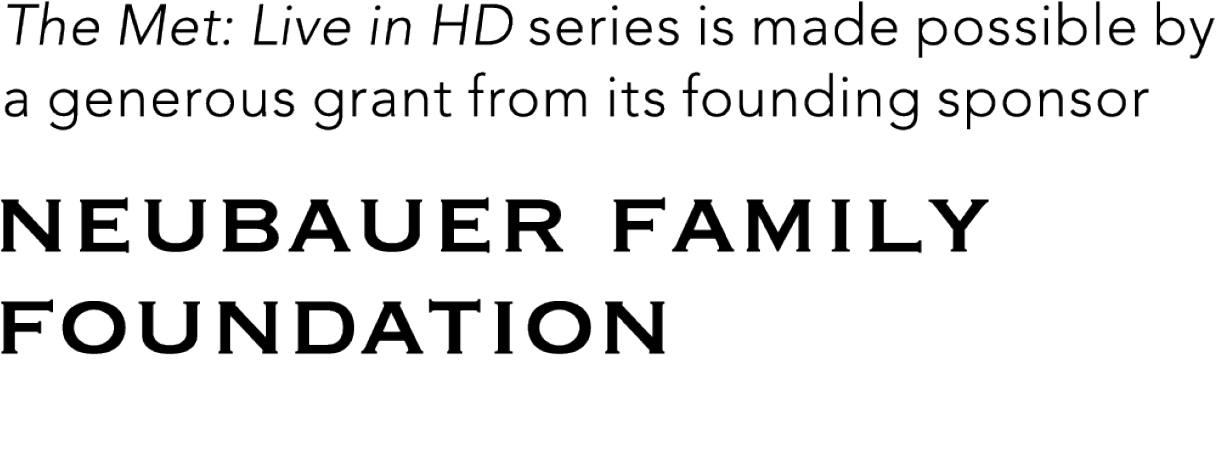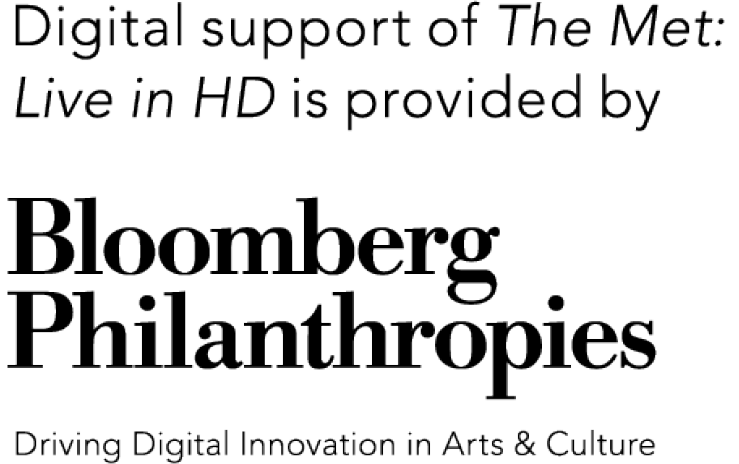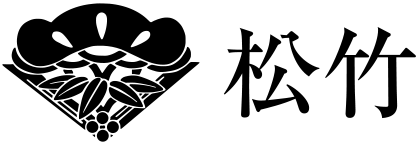《ランメルモールのルチア》みどころレポート
オペラ評論家 香原斗志
 磨かれた声を思う存分味わえる。《ランメルモールのルチア》の魅力は、たしかにそこにもあるけれど、じつは描かれた悲劇的な感情は底知れないほど深く、すぐれた上演に出逢うと幾重にも打ちのめされてしまう。METの新しい《ルチア》が、まさにそういう舞台だった。
磨かれた声を思う存分味わえる。《ランメルモールのルチア》の魅力は、たしかにそこにもあるけれど、じつは描かれた悲劇的な感情は底知れないほど深く、すぐれた上演に出逢うと幾重にも打ちのめされてしまう。METの新しい《ルチア》が、まさにそういう舞台だった。
元来の舞台は17世紀のスコットランド。落ち目の家を再興したい兄エンリーコは、妹ルチアに政略結婚を強いるが、彼女は家の敵エドガルドと将来を誓い合っていた。そこでエンリーコは策を弄し、妹を望まない結婚へと導くが、その結果、彼女は発狂して新郎を殺してしまい、ルチアが息絶えたのを知ったエドガルドは自ら命を断つ――。
 描かれている感情は生々しいが、それにしては、歌手の技巧を味わうだけのオペラだと誤解している人も多い。だが、サイモン・ストーンの新演出では悲劇の核心に生気みなぎるリアリティが与えられた。
描かれている感情は生々しいが、それにしては、歌手の技巧を味わうだけのオペラだと誤解している人も多い。だが、サイモン・ストーンの新演出では悲劇の核心に生気みなぎるリアリティが与えられた。
舞台が移されたのは現代のアメリカ中部の、犯罪や無気力、薬物中毒が蔓延するさびれた工業地帯。オリジナルの舞台とは遠いようで案外共通している。落ち目のマフィアのエンリーコは裕福な家にルチアを嫁がせ、その資金で組織を立て直そうとしているのだ。
 この舞台では現代の衣装をまとったルチアも、エドガルドも、エンリーコも、舞台でありながら表情も動きも映画を超えるほどリアルで、さらにルチアに焦点を当てたライブ映像が舞台上のスクリーンに映し出される。だから小さな表情から動きまで映画を超えるほどリアルに表現している。観客は感情移入を強いられ、もはや拒むことはできない。それに細部まで凝っている実例を挙げれば、エンリーコは全身にリアルなタトゥーが彫られ、描くのにも消すのにも40分かかるという。
この舞台では現代の衣装をまとったルチアも、エドガルドも、エンリーコも、舞台でありながら表情も動きも映画を超えるほどリアルで、さらにルチアに焦点を当てたライブ映像が舞台上のスクリーンに映し出される。だから小さな表情から動きまで映画を超えるほどリアルに表現している。観客は感情移入を強いられ、もはや拒むことはできない。それに細部まで凝っている実例を挙げれば、エンリーコは全身にリアルなタトゥーが彫られ、描くのにも消すのにも40分かかるという。
こうした演出が生えるのも音楽の水準が高いからだ。まずリッカルド・フリッツァの、各歌手の呼吸を見事に活かした生命力のある指揮が見事。カットされることが多い細部も極力生かされ聴き応えがある。
 そしてルチア役のネイディーン・シエラ。私はイタリアで2017年、同じフリッツァの指揮でシエラが歌うルチアを聴き、彼女は「時代を代表するルチア歌いになる」と確信し、その通りになった。見事なコロラトゥーラ、余裕ある高音はもちろん、シエラの歌はしなやかで、なめらかで、ニュアンスが豊かだ。声は5年前より充実し、ルチアの感情がすみずみまで豊かに描かれ、〈狂乱の場〉は完璧な歌唱に劇的表現力も加わって圧巻だった。
そしてルチア役のネイディーン・シエラ。私はイタリアで2017年、同じフリッツァの指揮でシエラが歌うルチアを聴き、彼女は「時代を代表するルチア歌いになる」と確信し、その通りになった。見事なコロラトゥーラ、余裕ある高音はもちろん、シエラの歌はしなやかで、なめらかで、ニュアンスが豊かだ。声は5年前より充実し、ルチアの感情がすみずみまで豊かに描かれ、〈狂乱の場〉は完璧な歌唱に劇的表現力も加わって圧巻だった。
 現代のテノールのなかで最も研ぎ澄まされた技巧を備えるハビエル・カマレナも、美しい歌唱と豊かで複雑な感情が両立した理想のエドガルドだ。ルチアとの二重唱では多くのテノールが省略するEs(ミ♭)の超高音を余裕で響かせ、声による鳥肌が立つほどの快楽も得られる。エンリーコのアルトゥール・ルチンスキーも、凄みがスタイリッシュに引き出され、これ以上は望めない水準だ。
現代のテノールのなかで最も研ぎ澄まされた技巧を備えるハビエル・カマレナも、美しい歌唱と豊かで複雑な感情が両立した理想のエドガルドだ。ルチアとの二重唱では多くのテノールが省略するEs(ミ♭)の超高音を余裕で響かせ、声による鳥肌が立つほどの快楽も得られる。エンリーコのアルトゥール・ルチンスキーも、凄みがスタイリッシュに引き出され、これ以上は望めない水準だ。
音楽的にも演劇的にもこうして掘り下げられると、このオペラが秘めた悲劇的な深みは、いやがおうにも浮き彫りになる。「これこそ泣けるオペラ」と気づく人が続出するのではないだろうか。