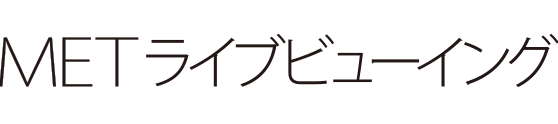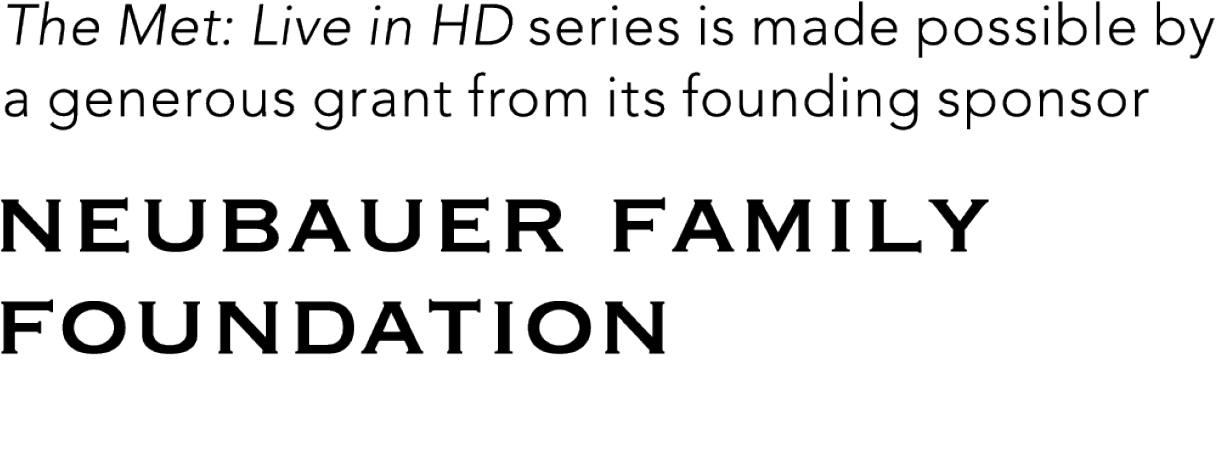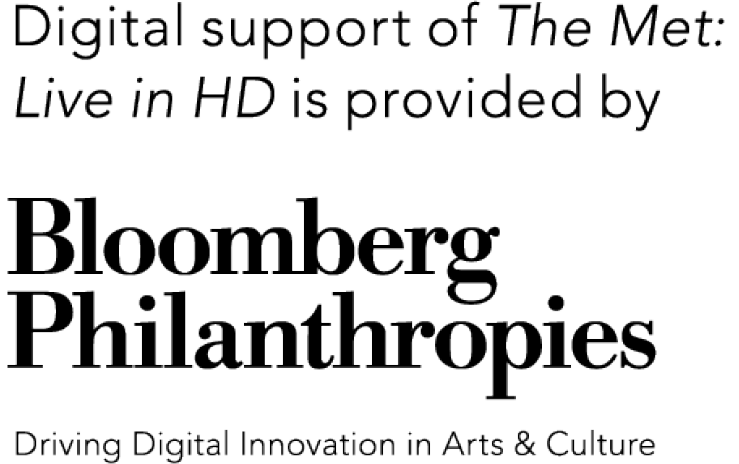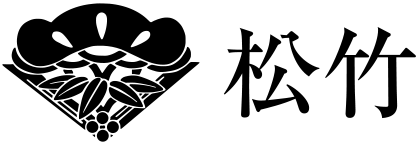《ドン・カルロス》みどころレポート
音楽評論家 石戸谷結子
 ヴェルディで最も好きなオペラは?と問われれば、「ドン・カルロ」と答える人が絶対に多いはず(じつは私もそうです)。16世紀のスペイン王室を舞台に、政治と宗教対立、父王と王子の葛藤に加え、王妃と王子の道ならぬ恋という大悲恋をメインテーマにした壮大なスケールの歴史大河ドラマだからだ。今回はMETでは初となるフランス語5幕版での上演だけに、大注目を集めた公演となった。
ヴェルディで最も好きなオペラは?と問われれば、「ドン・カルロ」と答える人が絶対に多いはず(じつは私もそうです)。16世紀のスペイン王室を舞台に、政治と宗教対立、父王と王子の葛藤に加え、王妃と王子の道ならぬ恋という大悲恋をメインテーマにした壮大なスケールの歴史大河ドラマだからだ。今回はMETでは初となるフランス語5幕版での上演だけに、大注目を集めた公演となった。
1867年に「ドン・カルロス」がパリ・オペラ座で初演された時は、フランス語5幕版で上演された。バレエ・シーンも入るグランド・オペラ様式だったため、上演時間が長く、ヴェルディ自身がイタリア語4幕版に改訂した。自身による5幕版もあり、METでは40年前のジョン・デクスター演出でも伊語5幕版を採用、2010年のニコラス・ハイトナー新演出でも同じ版と、5幕版は「METの伝統」でもあるのだ。2月末にプレミエを迎えたマクヴィカー新演出はどんな舞台だったのか?
 幕が開くとそこはフォンテンブローの森。スペインの王子ドン・カルロスとフランス王女エリザベートがここで出会い、ひと目で恋に落ちる。許嫁の二人は幸せにひたったが、すぐに不幸が直撃する。なんと王女はドン・カルロスの実の父であるスペイン王に嫁ぐことになったのだ。愛し合う二人は義理の母と息子という関係に。この第1幕があることで、その後のドラマに真実味と悲劇性が加わるのだ。ドン・カルロスは実らぬ不倫の愛に絶望し、王は息子と王妃の不穏な関係に悩む。
幕が開くとそこはフォンテンブローの森。スペインの王子ドン・カルロスとフランス王女エリザベートがここで出会い、ひと目で恋に落ちる。許嫁の二人は幸せにひたったが、すぐに不幸が直撃する。なんと王女はドン・カルロスの実の父であるスペイン王に嫁ぐことになったのだ。愛し合う二人は義理の母と息子という関係に。この第1幕があることで、その後のドラマに真実味と悲劇性が加わるのだ。ドン・カルロスは実らぬ不倫の愛に絶望し、王は息子と王妃の不穏な関係に悩む。
 演出家のマクヴィカーはMETの大舞台をフルに使い、威圧感のある重厚な雰囲気の舞台を創りあげた。宗教戦争が重くのしかかる16世紀のスペイン王室の中で、登場人物たちは愛と自身のアイデンティティーに激しく苦悩する。全幕には宗教対立の悲壮感が色濃く漂い、現在のウクライナ情勢とその悲劇をも想い起こさせる、マクヴィカーの現代感覚が強く反映されたスケールの大きい優れた舞台となった。
演出家のマクヴィカーはMETの大舞台をフルに使い、威圧感のある重厚な雰囲気の舞台を創りあげた。宗教戦争が重くのしかかる16世紀のスペイン王室の中で、登場人物たちは愛と自身のアイデンティティーに激しく苦悩する。全幕には宗教対立の悲壮感が色濃く漂い、現在のウクライナ情勢とその悲劇をも想い起こさせる、マクヴィカーの現代感覚が強く反映されたスケールの大きい優れた舞台となった。
 今回の公演で特筆したいのが、歌手たちの圧倒的な歌唱だ。まずはヨンチェヴァが堂々とした存在感と豊かな声量、深い表現力で、悲劇の王妃を演じ切った。ポレンザーニはフランス語に良く合った繊細で明るい優雅な声で、気弱なドン・カルロスの心理を見事に表現した。ロドリーグ役のデュピュイもまた、明るい響きのバリトン。二人による友情のニ重唱は、まるで美少年同士の純愛のように見えてくる。代役で登場した、エボリ公女役のジェイミー・バートンも迫力ある歌唱で「呪わしき美貌」を絶唱し、大喝采を受けた。
今回の公演で特筆したいのが、歌手たちの圧倒的な歌唱だ。まずはヨンチェヴァが堂々とした存在感と豊かな声量、深い表現力で、悲劇の王妃を演じ切った。ポレンザーニはフランス語に良く合った繊細で明るい優雅な声で、気弱なドン・カルロスの心理を見事に表現した。ロドリーグ役のデュピュイもまた、明るい響きのバリトン。二人による友情のニ重唱は、まるで美少年同士の純愛のように見えてくる。代役で登場した、エボリ公女役のジェイミー・バートンも迫力ある歌唱で「呪わしき美貌」を絶唱し、大喝采を受けた。
フランス語版は全体の響きが優雅で、力強いイタリア語とは印象が異なり、人物の性格表現が聴き手に深く迫ってくる。重厚な歴史物語というよりも、王妃エリザベートと王子ドン・カルロスの秘めた愛や、ドン・カルロスとロドリーグの純愛など、「愛のドラマ」に重点が置かれている。そしてマクヴィカー演出の最大の見どころはラスト・シーン。これまで見たことのない、あっと驚く感動の幕切れを、ぜひともお見逃しなく!