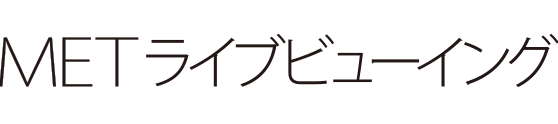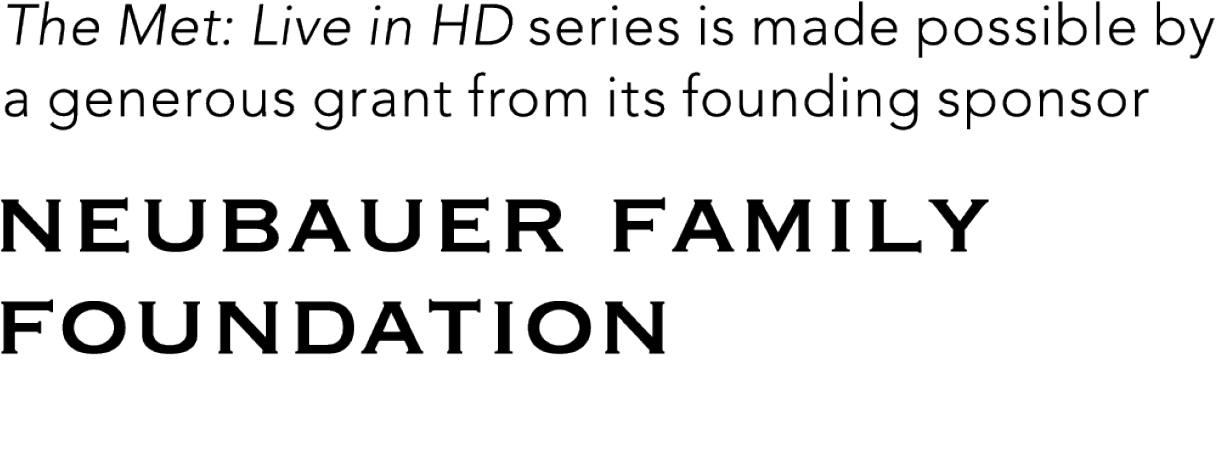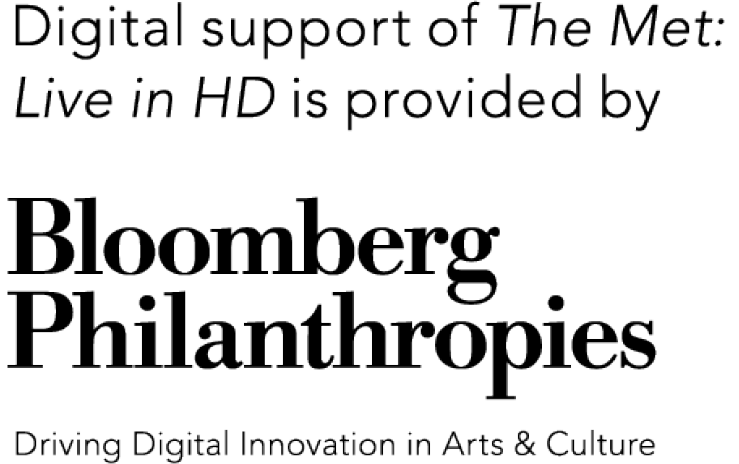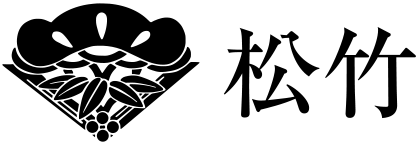《リゴレット》みどころレポート
オペラ評論家 香原斗志
 正味2時間ほどの密度が、ヴェルディ《リゴレット》ほど高いオペラはないが、なかでもこの舞台は極めつけだ。このオペラにみなぎる異常な感情やゆがんだ人間関係が、鮮やかに浮かび上がっていた。
正味2時間ほどの密度が、ヴェルディ《リゴレット》ほど高いオペラはないが、なかでもこの舞台は極めつけだ。このオペラにみなぎる異常な感情やゆがんだ人間関係が、鮮やかに浮かび上がっていた。
主人公のリゴレットは北伊マントヴァの宮廷の道化。人をダシに笑いをとっては恨みを買っている人物だ。それ以前のオペラの主人公は王侯貴族や英雄が多かったのとくらべれば、あまりにも異端者だが、だからこそ人間ドラマが深くなる。
もう少し筋書きに触れよう。リゴレットは仕えているマントヴァ公爵がひどい女たらしで、一人娘のジルダをもてあそんだので許せず、殺し屋を雇って公爵を殺そうとするが、公爵を愛してしまったジルダが身代わりになって殺される――。
 ストーリーには救いがまったくない。しかし、主役3人はキャラが立ち、リゴレットの怨念、父娘の愛情、能天気な暴君を愛してしまった娘の葛藤などが、ドラマと一体化して畳みかける音楽の力を得て鮮やかな印象を残す。もちろん、「鮮やかな印象」の度合いは音楽次第だが、今回のレベルで演奏されると、観る人は異常な世界に完全に引きずり込まれてしまうだろう。
ストーリーには救いがまったくない。しかし、主役3人はキャラが立ち、リゴレットの怨念、父娘の愛情、能天気な暴君を愛してしまった娘の葛藤などが、ドラマと一体化して畳みかける音楽の力を得て鮮やかな印象を残す。もちろん、「鮮やかな印象」の度合いは音楽次第だが、今回のレベルで演奏されると、観る人は異常な世界に完全に引きずり込まれてしまうだろう。
 リゴレット役は声を張り上げ、感情をあらわに歌われることが多い。だが、クイン・ケルシー(バリトン)はピアニッシモを多用し、弱さを強調して歌った。浮かび上がったのは、娘を溺愛するあまりに絶望している内省的な人物像で、それはピョートル・ベチャワ(テノール)の能天気なマントヴァ公爵との対比でなおさら強調された。こうなるとドラマは深まっていく。
リゴレット役は声を張り上げ、感情をあらわに歌われることが多い。だが、クイン・ケルシー(バリトン)はピアニッシモを多用し、弱さを強調して歌った。浮かび上がったのは、娘を溺愛するあまりに絶望している内省的な人物像で、それはピョートル・ベチャワ(テノール)の能天気なマントヴァ公爵との対比でなおさら強調された。こうなるとドラマは深まっていく。
なかでも出色だったのはジルダ役のイタリアのソプラノ、ローザ・フェオラだ。彼女の歌はパンデミックの前にヨーロッパで何度か聴いて、大のお気に入りだが、さらに進化していて驚いた。弱音の美しさも、高音の響きの純粋さも理想的で、声のすみずみまでコントロールが行き届いて、千々に揺れる女心を描き尽くした。それにフェオラが軸になると、二重唱も四重唱も美しいこと。
 歌の美しさが際立ったのは、指揮者ダニエレ・ルスティオーニの功績でもある。《リゴレット》は演奏の際に慣習的にカットされる部分が多く、また、どの歌手もヴェルディの指定を無視して声の力を誇示するように歌う傾向があるが、作曲者の意図に忠実に曲を作り上げていた。しかも、ドラマのツボを見事に見つけて音楽に変幻自在に起伏をつけていく。同世代のトップを走るこの若手は、以前、指揮界の最高峰に登り詰めると私に宣言したが、やはりただ者ではない。
歌の美しさが際立ったのは、指揮者ダニエレ・ルスティオーニの功績でもある。《リゴレット》は演奏の際に慣習的にカットされる部分が多く、また、どの歌手もヴェルディの指定を無視して声の力を誇示するように歌う傾向があるが、作曲者の意図に忠実に曲を作り上げていた。しかも、ドラマのツボを見事に見つけて音楽に変幻自在に起伏をつけていく。同世代のトップを走るこの若手は、以前、指揮界の最高峰に登り詰めると私に宣言したが、やはりただ者ではない。
舞台を16世紀から1920年代のワイマールに移したバートレット・シャーの新演出も説得力がある。それはファシズム前夜の、欺瞞に満ちた指導者たちが信頼を失った時代。公爵の異常さと、それがもとで起きる悲劇に説得力が得られる時代でもある。独裁者が侵略戦争の暴挙に出そうな空気という点でも、ロシアが暴発しているいま、考えさせられることが多かった。