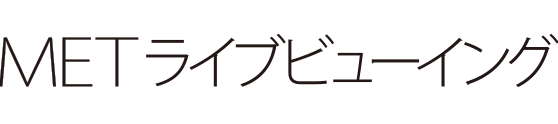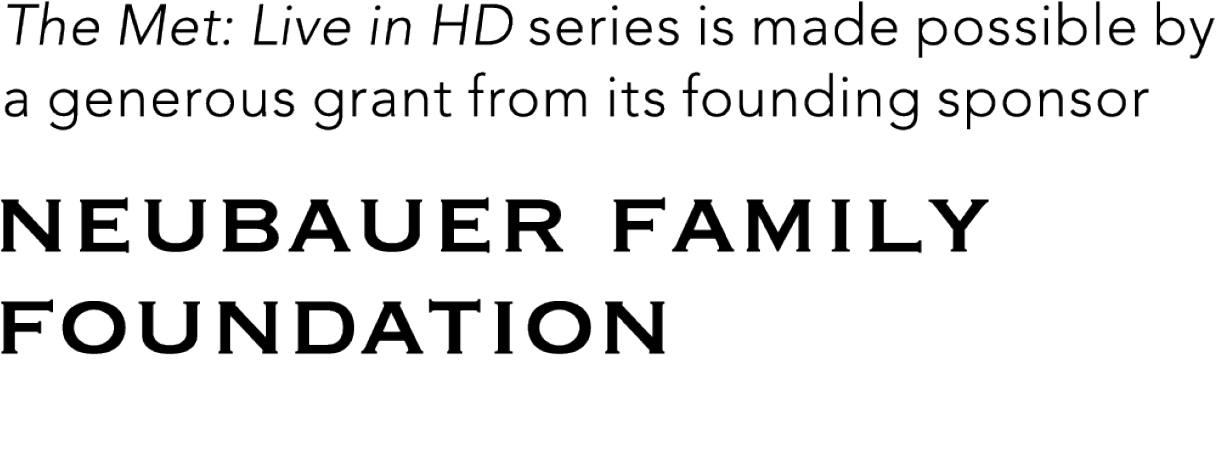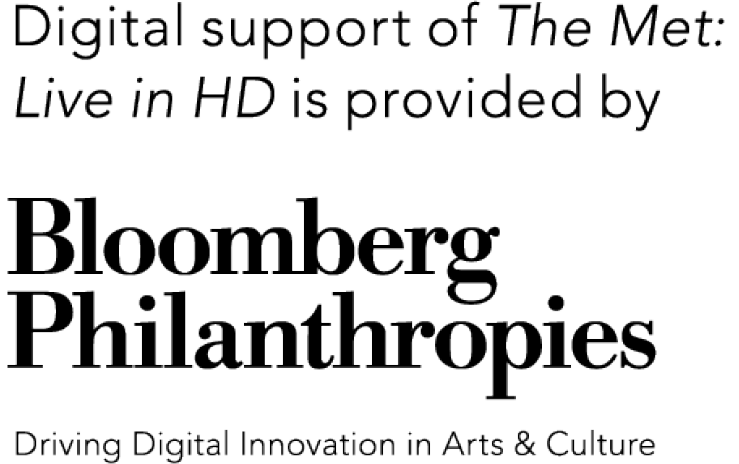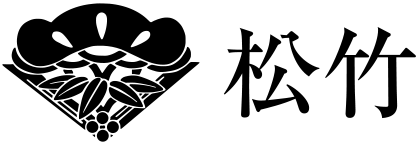《エウリディーチェ》みどころレポート
音楽ライター 小室敬幸
 Wikipedia英語版の「List of Orphean operas」によれば、オルフェオとエウリディーチェを題材にしたオペラの数は、17世紀までに20作、18世紀に28作、19世紀に7作、20世紀に14作、21世紀に4作にも上る。未完成作品なども含んでいるので完璧なリストではないが、この物語がいかに音楽家と台本作家の創意を刺激してきたかをお分かりいただけるだろう。
Wikipedia英語版の「List of Orphean operas」によれば、オルフェオとエウリディーチェを題材にしたオペラの数は、17世紀までに20作、18世紀に28作、19世紀に7作、20世紀に14作、21世紀に4作にも上る。未完成作品なども含んでいるので完璧なリストではないが、この物語がいかに音楽家と台本作家の創意を刺激してきたかをお分かりいただけるだろう。
オルフェオとエウリディーチェの最新のオペラ化である今回のMETライブビューイングで上映されるマシュー・オーコイン作曲『エウリディーチェ』は、2020年2月にロサンゼルス・オペラで世界初演されたばかり。共同委嘱をおこなったMETではこれが初上演となる。
 1990年生まれのオーコインは、まだ32歳ながら早熟で天才的なオペラ作曲家として注目を集める存在だ。オルフェオとエウリディーチェ物語が何故これほどまでにオペラの題材になってきたのか問われた彼は「人間と本質と音楽について真理を伝えている点です。音楽は死に打ち勝てますが、人間がいつも台無しにするのです。残酷なまでに正しい描写だと思います」と答えている。
1990年生まれのオーコインは、まだ32歳ながら早熟で天才的なオペラ作曲家として注目を集める存在だ。オルフェオとエウリディーチェ物語が何故これほどまでにオペラの題材になってきたのか問われた彼は「人間と本質と音楽について真理を伝えている点です。音楽は死に打ち勝てますが、人間がいつも台無しにするのです。残酷なまでに正しい描写だと思います」と答えている。
この説明を本作に沿って理解するならば、作曲家の死後も楽譜に書かれた音楽、もしくは録音物は残るはずだが、それを受け取った側が残された記録(≒楽譜、録音、テクスト、メッセージ)の意味や価値を理解できず、足蹴にしてしまう……ということになるだろう。戦火によって貴重な文化遺産が失われたり、独裁政権になった途端、国家的遺産が壊されたりする哀しい例は何度も繰り返されている。作り手の思いが受け手に伝わらないという悲劇。それは芸術作品のみでなくごく普通の人間生活にもひろく起こりうることであり、本作の終幕でもそれが残酷なまでに描きあげられている。
 もうひとつ、今回のオペラ化で重要になるのが「視点の反転」だ。オルフェオではなくエウリディーチェを主人公とする翻案は、そもそもこのオペラのためにされたわけではなく、原作かつこのオペラの台本も手掛けているサラ・ルールが2003年に発表した戯曲である。アメリカ国内で高く評価され、現在は高校や大学の演劇でも取り上げられるレパートリーとなっている。女性側の視点のみならず、死者の視点でオルフェオとエウリディーチェを再解釈した点が非常に新しかった。
もうひとつ、今回のオペラ化で重要になるのが「視点の反転」だ。オルフェオではなくエウリディーチェを主人公とする翻案は、そもそもこのオペラのためにされたわけではなく、原作かつこのオペラの台本も手掛けているサラ・ルールが2003年に発表した戯曲である。アメリカ国内で高く評価され、現在は高校や大学の演劇でも取り上げられるレパートリーとなっている。女性側の視点のみならず、死者の視点でオルフェオとエウリディーチェを再解釈した点が非常に新しかった。
 ひとつここで考えてみてほしいのが、今も生きている私たちは、既に亡くなってしまった大事な人々のことをどのくらい意識すべきなのか?ということだ。今なお続くパンデミックや、自然災害、あるいはより個人的な喪失を念頭に置いても構わない。喪失から時間がさほど経っていなければ、忘れたくても忘れられないのが当然である。しかし1年、3年、10年……と年月を経るごとに、記憶が薄れていくのが人間というもの。忘れるべきではないという意見ももちろんあるし、記憶を手放さなければ生きているのがツラいという現実もあるだろう。
ひとつここで考えてみてほしいのが、今も生きている私たちは、既に亡くなってしまった大事な人々のことをどのくらい意識すべきなのか?ということだ。今なお続くパンデミックや、自然災害、あるいはより個人的な喪失を念頭に置いても構わない。喪失から時間がさほど経っていなければ、忘れたくても忘れられないのが当然である。しかし1年、3年、10年……と年月を経るごとに、記憶が薄れていくのが人間というもの。忘れるべきではないという意見ももちろんあるし、記憶を手放さなければ生きているのがツラいという現実もあるだろう。
 この翻案を通してサラ・ルールは、それは死者にとっても同じことではないのかと突きつけてくる。詳しくはオペラ本編をご覧いただきたいが、本作においては「シャワー」が重要な意味をもつ。シャワーそのものだけでなく、「降る」「落ちる」というニュアンスも持っている言葉であり、更に冥界におけるシャワーは、その水を飲むと生前のことを忘れる「レテの川」(日本における三途の川に相当)として描かれるのだ。最終的にこのオペラでは、喪失という悲劇によってまた新たな悲劇が生まれ、胸が苦しくなるほどの結末を迎える。だが同時に「だからこそ過去にとらわれすぎず、前を向いて歩いてゆくべきだ」という実にポジティブなメッセージを、今を生きる我々には投げかけてくれるはずだ。
この翻案を通してサラ・ルールは、それは死者にとっても同じことではないのかと突きつけてくる。詳しくはオペラ本編をご覧いただきたいが、本作においては「シャワー」が重要な意味をもつ。シャワーそのものだけでなく、「降る」「落ちる」というニュアンスも持っている言葉であり、更に冥界におけるシャワーは、その水を飲むと生前のことを忘れる「レテの川」(日本における三途の川に相当)として描かれるのだ。最終的にこのオペラでは、喪失という悲劇によってまた新たな悲劇が生まれ、胸が苦しくなるほどの結末を迎える。だが同時に「だからこそ過去にとらわれすぎず、前を向いて歩いてゆくべきだ」という実にポジティブなメッセージを、今を生きる我々には投げかけてくれるはずだ。