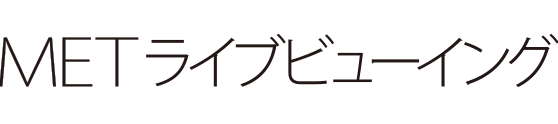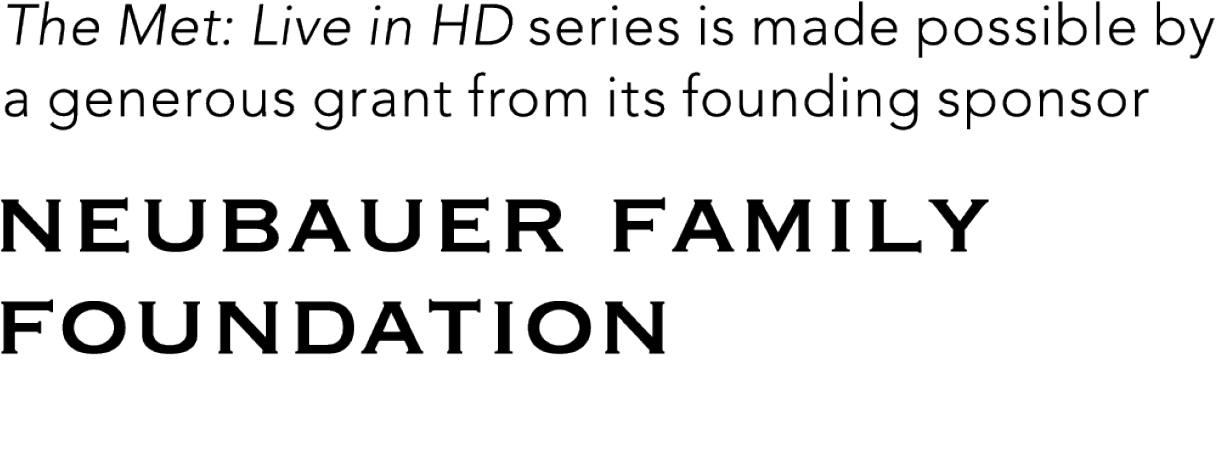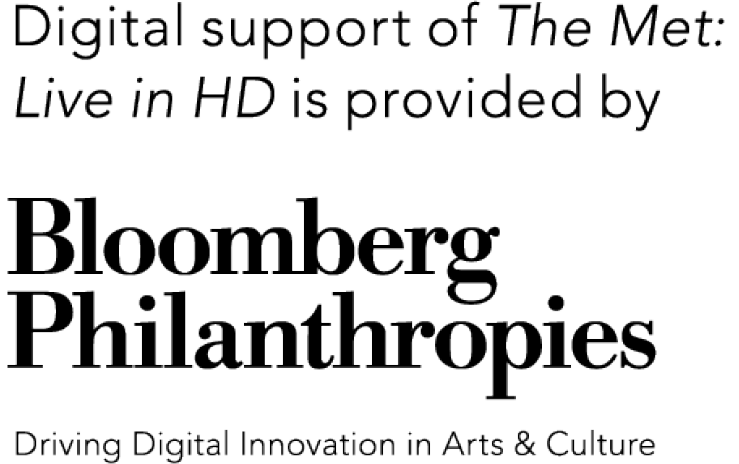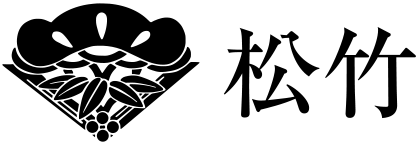《ボリス・ゴドゥノフ》みどころレポート
音楽評論家 堀内修
メトロポリタン・オペラの《ボリス・ゴドゥノフ》
 夜明けはこない。《ボリス・ゴドゥノフ》は皇帝ボリスの死で暗く終る。終りだけじゃない。METの《ボリス》は最初から暗い。ボリスが皇帝になってから死ぬまでの物語なのだが、民衆に望まれて戴冠する時から、ボリスは不安にさいなまれている。聴いているといつのまにかロシアの動乱時代を生きている気になる。それなのに幕がおりて緊張から解放されると清々しい気分になるのはなぜなのだろう?
夜明けはこない。《ボリス・ゴドゥノフ》は皇帝ボリスの死で暗く終る。終りだけじゃない。METの《ボリス》は最初から暗い。ボリスが皇帝になってから死ぬまでの物語なのだが、民衆に望まれて戴冠する時から、ボリスは不安にさいなまれている。聴いているといつのまにかロシアの動乱時代を生きている気になる。それなのに幕がおりて緊張から解放されると清々しい気分になるのはなぜなのだろう?
 派手な歴史絵巻として上演されることもあるオペラだけれど、METはムソルグスキーの1869年初稿版を使って、まったく違う《ボリス》を提示する。サンクトペテルブルグの歌劇場が常識はずれだと上演を拒否した版だ。ほとんど女性が舞台に登場せず、のオペラは休みなく一気に進む。ヴェルディ《ドン・カルロス》を断固として5幕版で上演してきたMETは、(今シーズンはさらに原点に戻ってフランス語5幕版になる)これこそが本当の《ボリス・ゴドゥノフ》だと、その見識を誇示する。
派手な歴史絵巻として上演されることもあるオペラだけれど、METはムソルグスキーの1869年初稿版を使って、まったく違う《ボリス》を提示する。サンクトペテルブルグの歌劇場が常識はずれだと上演を拒否した版だ。ほとんど女性が舞台に登場せず、のオペラは休みなく一気に進む。ヴェルディ《ドン・カルロス》を断固として5幕版で上演してきたMETは、(今シーズンはさらに原点に戻ってフランス語5幕版になる)これこそが本当の《ボリス・ゴドゥノフ》だと、その見識を誇示する。
 戴冠の場で鳴り響く祝いの鐘がはっきりと弔鐘として聴こえる時には、その見識を受け入れざるを得なくなるはずだ。
戴冠の場で鳴り響く祝いの鐘がはっきりと弔鐘として聴こえる時には、その見識を受け入れざるを得なくなるはずだ。
METの初稿版《ボリス》には2人の主役が舞台に登場する。1人はもちろんボリスだ。先帝の皇子を殺害した罪におののき、不安にかられながら帝位に就いた男をルネ・パーペが歌う。この役で世界を征服した伝説のバス、シャリアピンの後継者にふさわしいのではないだろうか?〈ボリスの死〉の場はパーペの歌の演技にかかっている。
もう1人の主役というべきロシアの民衆を歌うのは、METの合唱団に決っている。いつもの朗々とした「METの合唱」とは一味違うスリムな暗い色調の歌で勝負する。
 さらにセバスティアン・ヴァイグレの指揮が上演の方向を決定づける。ワーグナーの指揮で日本でも定評のあるヴァイグレは、その明快な指揮で初稿版《ボリス》の斬新さを浮き彫りにする。アリアとレチタティーヴォで構成する伝統的なやり方を離れ、場面ごとに音楽を作り上げていった結果が歴然と聴き取れる。継ぎ目のない場面の連鎖を、宮廷歌劇場はもちろん、改訂したリムスキー=コルサコフさえ完全には理解しなかったのだろう。ドビュッシーが《ペレアスとメリザンド》で受け継いで広く認められたムソルグスキーの独創性が、ヴァイグレの指揮で露わになる。継ぎ目のない音楽による場面が7つ連なる《ボリス》を、METはさらに継ぎ目なく上演するものだから、その効果が一層生きてくる。
さらにセバスティアン・ヴァイグレの指揮が上演の方向を決定づける。ワーグナーの指揮で日本でも定評のあるヴァイグレは、その明快な指揮で初稿版《ボリス》の斬新さを浮き彫りにする。アリアとレチタティーヴォで構成する伝統的なやり方を離れ、場面ごとに音楽を作り上げていった結果が歴然と聴き取れる。継ぎ目のない場面の連鎖を、宮廷歌劇場はもちろん、改訂したリムスキー=コルサコフさえ完全には理解しなかったのだろう。ドビュッシーが《ペレアスとメリザンド》で受け継いで広く認められたムソルグスキーの独創性が、ヴァイグレの指揮で露わになる。継ぎ目のない音楽による場面が7つ連なる《ボリス》を、METはさらに継ぎ目なく上演するものだから、その効果が一層生きてくる。
ボリスが死ぬ。ロシアに夜明けはこない。《ボリス・ゴドゥノフ》は本物の悲劇だ。幕がおりた後、奇妙に清々しい気分になるのは、これが終わってしまった過去の悲劇ではないと覚悟できるからなのだろうか?