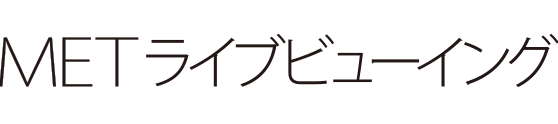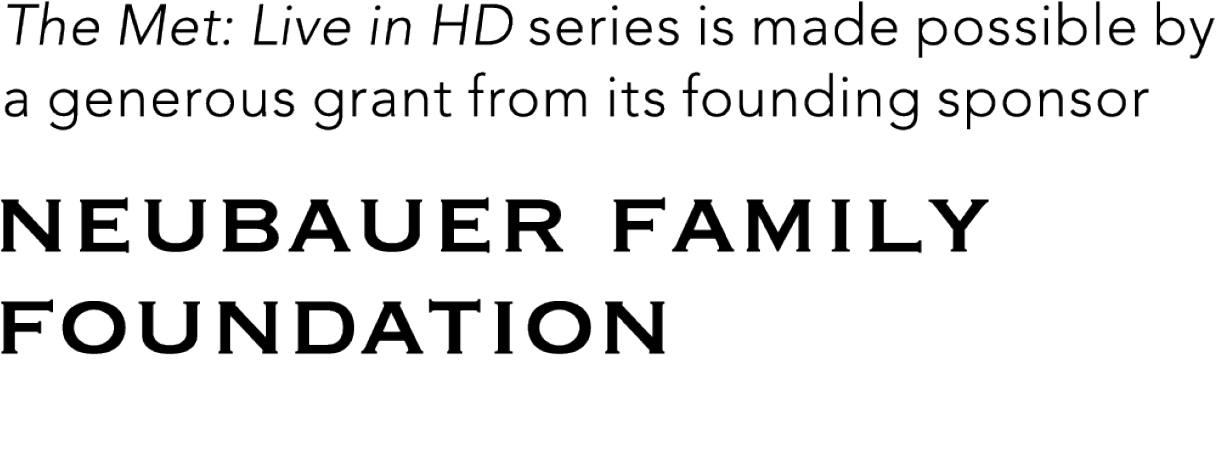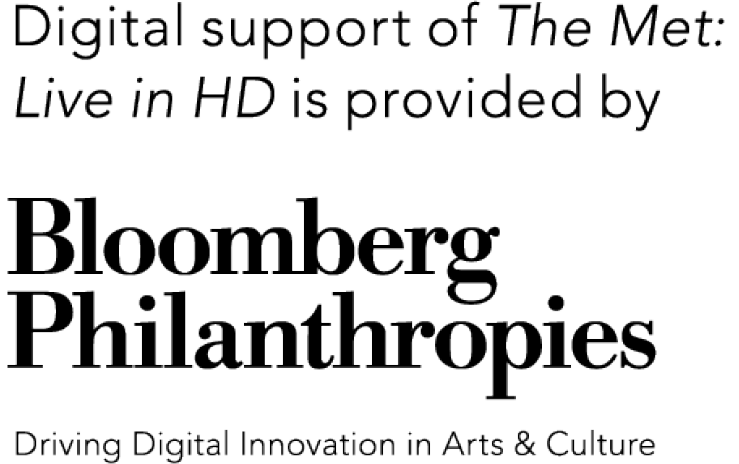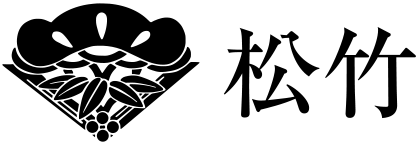《椿姫》新演出 みどころレポート
音楽評論家 加藤浩子
伝説の高級娼婦の「愛」と「死」を描いた名作中の名作に、あらたな伝説が誕生!

椿の花が咲いていた。
舞台上の空間に浮かび上がった、大輪の白い椿。伝説的なヒロインが愛したゆかりの花だ。花びらの縁はかすかなピンクに染まっていた。この世を去ろうとしているヒロインの、最後の鼓動のように。
ヴェルディの《椿姫》は、世界でもっとも上演回数が多い大人気オペラである。病を抱えて刹那的に生きる高級娼婦が、真実の愛を捧げてくれる恋人にめぐり逢い、つかの間の幸せに酔うが、世間体を重んじる恋人の父に別れを強要され、病の床で死んでゆく…。

王道の悲恋物語を、「乾杯の歌」「プロヴァンスの海と陸」をはじめ、誰もが耳にしたことのある名曲が彩る。何よりどの音も、登場人物の心やその場の展開を的確に伝えてくれるので、ドラマに引き込まれる。名作中の名作とされるのはもっともなのだ。
ヒロインのモデルは、19世紀のパリに実在した有名娼婦。あのフランツ・リストをも魅了した美貌の娼婦は、新進作家のデュマと恋に落ちてベストセラー小説「椿姫」を書かせた。ヴェルディはデュマの「椿姫」のヒロインに共感してオペラを書いた。ヴェルディの境遇はデュマと似ていた。彼は、男性遍歴で世間を騒がせたオペラ歌手の恋人と同棲していたのである。
 パリの有名娼婦は、椿の花を愛した。それも、白い椿を。今回新しく制作されたMETの《椿姫》は、全体をヒロインのヴィオレッタの回想として設定している(M・メイヤー演出)。第1幕の冒頭で浮かび上がるのは、彼女の命のシンボルのような椿の花。その花の下でヴィオレッタはベッドに横たわり、彼女を見守る人々に囲まれながら、愛の思い出に浸る。
パリの有名娼婦は、椿の花を愛した。それも、白い椿を。今回新しく制作されたMETの《椿姫》は、全体をヒロインのヴィオレッタの回想として設定している(M・メイヤー演出)。第1幕の冒頭で浮かび上がるのは、彼女の命のシンボルのような椿の花。その花の下でヴィオレッタはベッドに横たわり、彼女を見守る人々に囲まれながら、愛の思い出に浸る。
メイヤー演出は、恋の移り変わりを季節になぞらえた。春に出会い、夏にピークを迎え、秋に衰え、冬に終わる恋物語は、豪華なサロンとカラフルな衣装をとおして体現される。第2幕でヴィオレッタが恋人の父の説得に負け、別れを決意した瞬間、舞台の色合いが「夏」から「秋」に変わったのは衝撃的だった。台本には設定されていない恋人の妹を黙役で登場させたのも効果的。妹は最終幕にも立ち会い、彼女の「家」のために犠牲になったヒロインの最期を見届けるのである。

ヴィオレッタを歌ったD・ダムラウは、現在この役の第一人者だろう。美しくしなやかな声はありとあらゆる感情を鏡のように映し出し、迫真の演技と相まって心に響く。色鮮やかな衣装が入り乱れるなかで、ひとり白(一部金色)一色のドレスで通すのも印象的だ。
相手役のJ・D・フローレスは甘く輝かしい声で青年の一途な愛を歌い上げ、父親役のQ・ケルシーは、ヴィオレッタへの共感を隠せず苦悩する人間的な父親を創造した。《椿姫》には悪役はいない。それを痛感させてくれた最高のキャストだった。
舞台の「総仕上げ」の役割を果たしたのが、MET新音楽監督Y・ネゼ=セガンの指揮。これが音楽監督就任後初の指揮となるネゼ=セガンは、《椿姫》は「現存する音楽作品のなかでもっとも完璧な作品のひとつ」だと高く評価する。彼が作品を深く理解していることは、音楽が舞台と完璧に一体化していることからよく伝わってきた。すべての音が、名画を縁取る美しい額縁のように自然だったのだ。これこそ、理想的なオペラの指揮ではないだろうか。
初めてでも、何度見ても、心揺さぶられる《椿姫》。不朽の名作に、いま、新たな1ページが加わった。