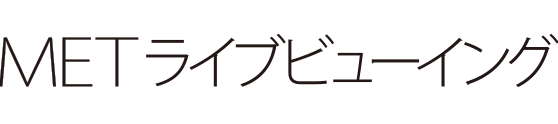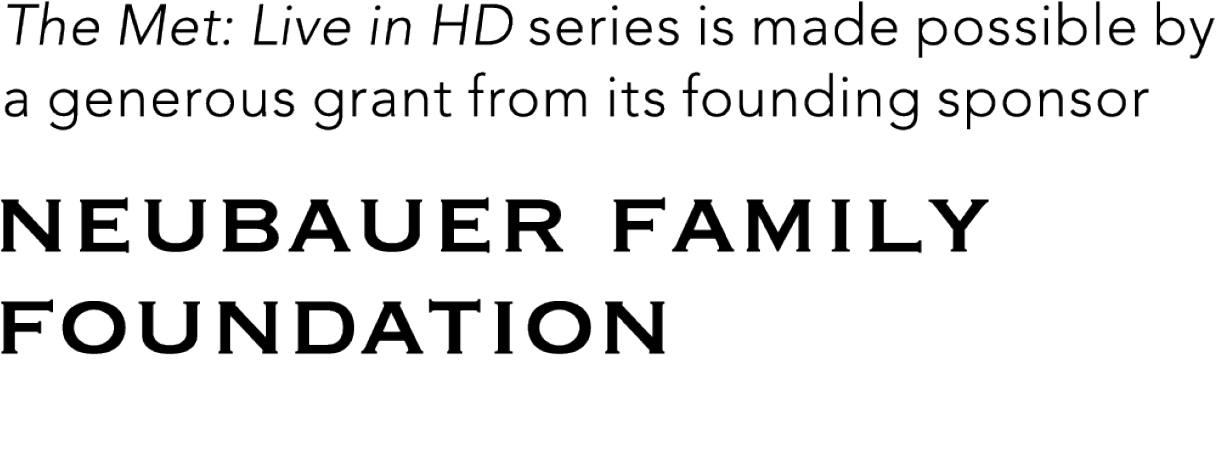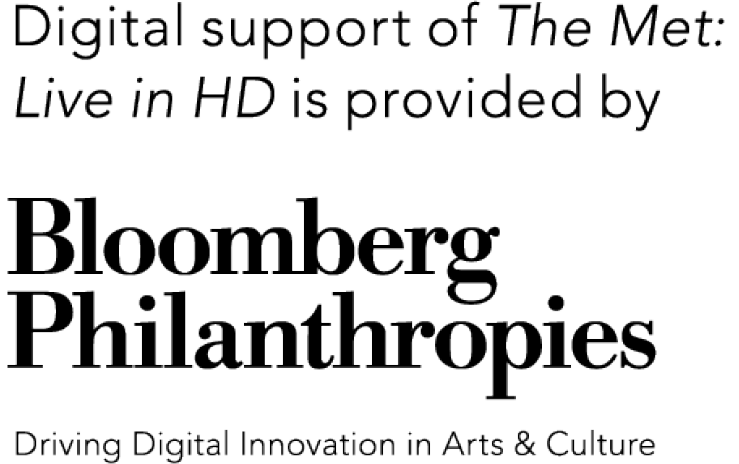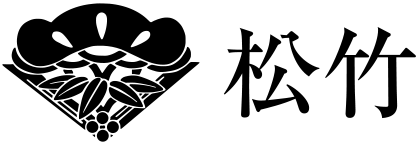《アイーダ》現地レポート
NY在住音楽ジャーナリスト 小林伸太郎
ヴェルディのオペラ《アイーダ》は、メトロポリタン歌劇場でも1886年の初演以来、上演1,200回に迫ろうとする人気オペラだ。しかし今年の上演は、発表されるやいなや、ただの人気オペラではなくなった。あのアンナ・ネトレプコが、タイトルロールを初めてMETで歌うことになったからだ。

ネトレプコにとってヴェルディ作品は、METでは13年前に初めて歌った《リゴレット》のジルダ、(METではまだ歌っていないものの)《椿姫》のヴィオレッタなど、キャリアの早い時期から全く馴染みがなかったわけではない。しかしここ数年のネトレプコが取り組むヴェルディ作品は、METでは4年前に初めて歌った《マクベス》のマクベス夫人、同じく3年前《イル・トロヴァトーレ》のレオノーラなど、かつては彼女が歌うことが想像できなかったような、より劇的な表現が要求されるものに急激に変化している。そのいわば「新しい」ネトレプコの声で、初めてアイーダを歌うというのだから、注目されて当然だろう。果たしてその期待は、裏切られなかった。
 ネトレプコがネトレプコであるのは、あの聴いただけですぐわかる、独特のカラーを持つ声にあると思う。そのカラーを保ちながら、ネトレプコはどこまでも伸びるヴェルディの劇的なラインを、実に音楽に忠実に、くっきりと歌う。第一幕のアリア<勝ちて帰れ>の劇的な激しさと葛藤はもちろんのこと、最大の聴きどころでもある第三幕<おお、我が祖国>の祈りも、美しく響くハイCと共に、誰のコピーでもない、彼女ならではの表現で聴かせる。いつもながらの嘘のない彼女の演技も見る者の心に響き、奴隷の身となったエチオピア王女、アイーダの悲劇を、絵空事でない親密さで伝えてくれた。
ネトレプコがネトレプコであるのは、あの聴いただけですぐわかる、独特のカラーを持つ声にあると思う。そのカラーを保ちながら、ネトレプコはどこまでも伸びるヴェルディの劇的なラインを、実に音楽に忠実に、くっきりと歌う。第一幕のアリア<勝ちて帰れ>の劇的な激しさと葛藤はもちろんのこと、最大の聴きどころでもある第三幕<おお、我が祖国>の祈りも、美しく響くハイCと共に、誰のコピーでもない、彼女ならではの表現で聴かせる。いつもながらの嘘のない彼女の演技も見る者の心に響き、奴隷の身となったエチオピア王女、アイーダの悲劇を、絵空事でない親密さで伝えてくれた。
 今回は、恋敵のエジプトの女王、アムネリスにアニータ・ラチヴェリシュヴィリを得たことも幸いした。昨シーズンの《イル・トロヴァトーレ》アズチェーナ役で、久しぶりにMETに真のヴェルディ・メッゾが現れたと評判になった彼女。劇的な激しさと柔らかさを同時に併せ持った幅広い表現で、当代一番のプリマドンナ、ネトレプコに激しく対抗して全く引けを取らない。第四幕のアムネリス最大の見せ場、ラダメスの審判の場のラチヴェリシュヴィリにも、大いに期待していただきたい。
今回は、恋敵のエジプトの女王、アムネリスにアニータ・ラチヴェリシュヴィリを得たことも幸いした。昨シーズンの《イル・トロヴァトーレ》アズチェーナ役で、久しぶりにMETに真のヴェルディ・メッゾが現れたと評判になった彼女。劇的な激しさと柔らかさを同時に併せ持った幅広い表現で、当代一番のプリマドンナ、ネトレプコに激しく対抗して全く引けを取らない。第四幕のアムネリス最大の見せ場、ラダメスの審判の場のラチヴェリシュヴィリにも、大いに期待していただきたい。
 その他、アイーダの父であるエチオピア国王、アモナズロを歌ったクイン・ケルシーの圧倒的な美声も聴きものであったし、ニコラ・ルイゾッティのグイグイと引っ張る指揮に、METのオーケストラとコーラスも絶好調だった。ソニヤ・フリゼル演出による、MET自慢の舞台機構を駆使した重厚な舞台も、初演30年を経た今、古びるどころか、永遠の美しさを獲得したような美しさを湛えていた(9月29日所見)。
その他、アイーダの父であるエチオピア国王、アモナズロを歌ったクイン・ケルシーの圧倒的な美声も聴きものであったし、ニコラ・ルイゾッティのグイグイと引っ張る指揮に、METのオーケストラとコーラスも絶好調だった。ソニヤ・フリゼル演出による、MET自慢の舞台機構を駆使した重厚な舞台も、初演30年を経た今、古びるどころか、永遠の美しさを獲得したような美しさを湛えていた(9月29日所見)。